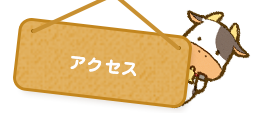写真=地元・JA鹿児島県経済連が開発した家畜ふん尿などを活用した有機質肥料のサンプルを手に効能を記者に説明する自民農林族最重鎮の森山裕氏
10月1日、石破茂新政権がスタートした。閣僚、党幹部とも自民農林幹部が重責を担う体制だ。今月27日に解散・総選挙がひかえる。「透視眼」10月号は岸田政権3年を検証するとともに、石破新政権の課題を探る。後半は、次期酪農肉用牛近代化基本方針(酪肉近)策定など酪農制度確立の動きを見る。
地方重視・石破氏の素顔
「透視眼」9月号に、たまたま石破茂氏と農業団体関係者とのカット写真を使った。自民総裁選決選投票で議員票が集まらず敗北するだろうと思い、その前に掲載したに過ぎない。結果は、自民党内の勢力相関図ではありえない、まさかの石破総裁の誕生である。偶然だが、まさに石破勝利を予言するような写真となった。政権維持へ自民党の〈疑似政権交代〉とも言えるだろう。
記者個人としては石破氏と互いに30代のころから30年以上の付き合いがある。衆院選時に地元鳥取1区の取材に行き、控えめな佳子夫人も間近に見た。地域の過疎化を誰よりも憂い、農業をはじめ第1次産業の振興を願っていた。勉強熱心で熱い方である。一言でいうと〈一言居士〉か。逆に言うと世渡り下手、空気が読めないKY的なところもある。それが、本人の政治家としての隘路にもつながってきた。
政治家は、政策面での考え方の違いで対立することもあるが、根っこのところはもっと人間くさい。気が合うかどうか、肌合いのところが大きい。その意味では、石破氏をそばで見てきた記者として、安倍晋三元首相と石破氏は本当に肌合いが違う、そりが合わない実感が強い。
30年以上前、よく石破氏の宿舎だった東京・九段の衆院議員宿舎の部屋を夜に訪ね、これからの農業・農政で語り合った。2015年5月、絶頂を極めた安倍政権下で初代地方創生大臣に就いた石破氏に宴席でこう言ったことがある。「このままでは安倍氏の下で飼い殺しになる。閣外に出るべきだ」と。その時はうなずきもせず黙って聞いていた。それから数か月後、閣外に去り安倍氏と対抗する形で事実上の派閥、石破派を立ち上げた。
農業団体が恐れた幻の「進次郎政権」
今回の総裁選で、農業団体が最も恐れたシナリオは、国民的な人気も高い小泉進次郎政権の誕生だ。石破氏自身、「少し前まで決選投票は小泉氏と戦うことになるのではないか」と語っている。「透視眼」9月号でも〈進次郎政権の組閣名簿〉にも触れた。
結局は、政策の稚拙さが露呈し失速した。幻となった「進次郎政権」で農業団体は何を懸念したのか。連呼した「聖域なき改革」に、10年前、2015年前後の安倍政権下での理不尽な「農政改革」「農協改革」「酪農制度改革」を重ね合わせたからだ。
当時、官房長官は農協嫌いの菅義偉氏、自民党は農林幹部・西川公也氏と小泉進次郎農林部会長が二人三脚となり、農水省は菅官邸人事で経営局長から事務次官へ昇格する奥原正明氏。TPP推進に反対した全中の農協法外し、全農の株式会社化検討、さらには現行指定団体制度廃止へと〈農政改悪〉は加速していく。改正畜安法は今日の生乳需給調整に大きな支障を招き禍根を残している。だが、誰も責任を取らない。
自民農林筆頭・森山幹事長の手腕に期待
総裁選の前半、小泉人気が盛り上がっていたころ、農業団体農政幹部に「進次郎政権になったらどうするつもりか」と尋ねた。すると「森山先生が農林トップとしている以上は心配ない」と応じた。その森山裕氏は党総務会長から自民党ナンバー2の幹事長に抜擢された。
1年ほど前に森山氏に石破評を直接聞いたことがある。「石破さんをどう思いますか。農政にも熱心ですがだめですか」とたずねると「いや、そんなことはない。能力は高いし人一倍勉強熱心な政治家だ」と応じた。ただ「時局を見る目、タイミング、発言が政治家としてどうかと思うこともある」とも付け加えた。それは森山氏の見立ての通りだろう。そんな直截な物言いが石破氏自身の常に跳ね返ってきた。石破氏と森山氏の関係は親密ではないが、悪い関係ではない。
石破新首相の基本姿勢は防衛とともに地方、農政重視の方向だ。そこで農林幹部が閣僚、党幹部にも配置された。官房長官は元農相の林芳正氏を続投、農相には党農林部会長、衆院農林水産委員長などを務め、岸田政権で首相補佐官だった小里泰弘氏が就いた。9月号で農林幹部がキーパンソンになると指摘したとおりだ。
こうした中で今後の政権運営を左右するのは森山氏だろう。菅氏や二階俊博元幹事長ら党重鎮と関係が深く、連立相手の公明党、野党ともパイプがある。相手の立場も踏まえ粘り強く説得する実務能力は、党内外で評価が高い。それに温厚な人格者なのも政治家としての評価を高めている。食料安全保障を前面に掲げた改正基本法制定を主導した森山氏の手腕に期待が高まる。ただ心配は、幹事長職が激務で、党の農政運営と関わる時間がなくなるのではないかという点だ。
改正基本法制定の岸田政権
ここで3年間の岸田政権を振り返ってみよう。総括的にはそれほど大きな政策ミスがあったわけではない。しかし、国民の人気は低く内閣支持率は低迷を続け、最終的に自民党内で「岸田氏では総選挙は戦えない」となり、総裁再選の道を自ら断った。
農政面では改正基本法制定など重要法案が成立した。しかしこれはあくまで理念法で、実際に国内農業振興、食料自給率の向上、国産シフトなど農政の魂を入れるのはこれからだ。具体化は先送りされたと言っていい。今、基本計画、次期酪肉近などを論議中で、石破新政権が具体的にどういった政策支援、予算措置をとるかにかかっている。
中酪、酪農制度確立で国に要請
酪肉近生乳目標780万トン念頭に
非系統含め需給調整枠組み構築急務
酪肉近生乳目標780万トン念頭に
非系統含め需給調整枠組み構築急務
次に酪農制度確立の話題に移ろう。
中央酪農会議は、農水省に改正食料。・農業・農村基本法や論議が始まった次期酪肉近を踏まえた酪農制度確立を要請した。国内酪農存続への喫緊の課題を網羅したものだ。次期酪肉近生乳目標は「増産型」維持を掲げた。非系統も含めた政府主導による全国的な生乳需給調整の枠組み構築も求めた。
危機打開へ5項目要求
当面の課題である12月中旬決定見込みの2025年度畜酪政策価格・関連対策をはじめ、今後10年間の政策方向を示す次期酪肉近、改正畜安法での問題点、「みどり戦略」の基づく環境調和型酪農対応など、解決すべき項目を具体的に整理、網羅した。底流を流れるのは、酪農家の離農に歯止めがかからない中での、国内酪農存立への強い危機意識だ。
〈改正基本法を踏まえた酪農制度確立の要求〉
① 生乳生産目標は生産意欲を損なわないよう消費拡大に注力しつつ増産型水準を設定
② 2025年度補給金単価は加工向け環境整備の水準、集送乳調整金は物流コスト上昇踏まえ適切な水準、交付対象数量は国内の生乳需給の実態を踏まえ
③ 合理的価格形成は生乳生産コストの変動を反映すること。指定団体外の自主流通拡大の中で自主流通事業者等を含めた全国的な枠組みでのセーフティーネット構築を含めた需給調整対策を確立
あわせて都府県不需要期における乳製品処理脆弱化への支援。あわせて無脂乳固形分や国産ナチュラルチーズ需要拡大への支援策確立
④ 「みどりの食料システム戦略」対応と持続的酪農経営を担保するため直接支払いも含めた政策支援の構築 また配合飼料価格安定制度による影響緩和機能の堅持と積立財源安定確保に向けた環境整備を促進
⑤ 国産飼料の生産拡大へ耕畜連携、コントラクター強化、適地適作・転作田の活用による飼料用米・稲発酵粗飼料(WCS=ホールクロップサイレージ)生産を含めた国産飼料生産の推進
① 生乳生産目標は生産意欲を損なわないよう消費拡大に注力しつつ増産型水準を設定
② 2025年度補給金単価は加工向け環境整備の水準、集送乳調整金は物流コスト上昇踏まえ適切な水準、交付対象数量は国内の生乳需給の実態を踏まえ
③ 合理的価格形成は生乳生産コストの変動を反映すること。指定団体外の自主流通拡大の中で自主流通事業者等を含めた全国的な枠組みでのセーフティーネット構築を含めた需給調整対策を確立
あわせて都府県不需要期における乳製品処理脆弱化への支援。あわせて無脂乳固形分や国産ナチュラルチーズ需要拡大への支援策確立
④ 「みどりの食料システム戦略」対応と持続的酪農経営を担保するため直接支払いも含めた政策支援の構築 また配合飼料価格安定制度による影響緩和機能の堅持と積立財源安定確保に向けた環境整備を促進
⑤ 国産飼料の生産拡大へ耕畜連携、コントラクター強化、適地適作・転作田の活用による飼料用米・稲発酵粗飼料(WCS=ホールクロップサイレージ)生産を含めた国産飼料生産の推進
「増産型」生産目標の維持を
次期酪肉近論議の焦点の一つが10年後の2035年度生乳生産目標の扱い。現行は2030年度目標で780万トン。Jミルクは戦略ビジョンで最大800万トンとした。半面、生乳需要が堅調だった5年前の情勢とは一変し脱粉過剰対策が続く。こうした中で中酪は、あくまで「増産型」を維持すべきとした。
生産目標をめぐっては関係者からさまざまな意見が出ている。一つは、脱粉過剰対策に伴い北海道での2年間にわたる苦渋の減産計画などの経過から、需給緩和を直視し現行目標を下回る「減産型」に転換すべきとの声だ。一方で、酪農家の生産意欲を損なわないためにも現行780万トンを念頭に、あくまで「増産型」を堅持すべきとの意見も強い。
中酪が「増産型」に固執するのも生産現場の意欲向上を踏まえた。改正基本法で食料安全保障構築が農政の柱に据えられ、持続的酪農経営を維持・強化し国産牛乳・乳製品の安定供給を進めるとの意思表示でもある。ここで重要なのは、「増産型」維持の大前提に「消費拡大に注力しつつ」として、あくまで国産生乳の需要拡大と並行した生産拡大を求めた点だ。
「みどり戦略」推進に直接支払い必要
環境負荷軽減へ農水省が推進する「みどり戦略」を踏まえ、中酪は酪農経営の持続的な維持・発展を担保するため直接支払いも含めた政策支援を求めた。ふん尿処理、牛のげっぷ対策など環境調和型農業を進めるにあたり、酪農経営のコスト増加が避けられないためだ。
「みどり戦略」に絡め、酪農直接支払いの具体的提案の一つでは乳牛1頭当たり単価で酪農家への直接給付方式などの意見も出ている。一定以上の乳質、オーガニック・放牧など「特色ある生乳」、アニマルウエルフェア、自給飼料生産、環境・気候変動対策、酪農教育ファーム実施など食育、6次産業化など実施する酪農家には単価加算して支給などだ。一部、予算化されているものもあるが、総合メニューとして酪農直接支払いの仕組みも重要となる。
政府主導の需給調整が不可欠
年間5%以上の離農が続き、指定団体の受託戸数が1万戸の大台割れになったとみられる酪農制度の安定的運用には、変動する生乳需給の対応が欠かせない。
改正基本法論議も踏まえ、畜産部会は3月から生産現場、業界関係者からヒアリングを重ねてきた。この前段ヒアリングで生乳需給調整の在り方で意見が相次いだ。
指定団体の関東生乳販連・迫田孝常務は「指定団体やこれに出荷する酪農家のみがリスクやコストなどを負担するのであれば需給調整機能は維持できない。酪農乳業者のすべてに参加を求めるルールが必要だ」、日本乳業協会・本郷秀毅常務は「酪農の安定のためには新商品開発や輸出拡大、需給と価格の安定、需給調整や経営安定対策、生産者間の不公平感の確保が欠かせない」と指摘した。一方で非系統の最大生乳集荷・卸業者MMJの藤本涼子氏は「自主流通の事業者も脱粉対策での拠出金を負担すべきとの意見があるが、自主流通の余乳を加工に回すなど最大限引き受けている」と反論している。
指定団体の関東生乳販連・迫田孝常務は「指定団体やこれに出荷する酪農家のみがリスクやコストなどを負担するのであれば需給調整機能は維持できない。酪農乳業者のすべてに参加を求めるルールが必要だ」、日本乳業協会・本郷秀毅常務は「酪農の安定のためには新商品開発や輸出拡大、需給と価格の安定、需給調整や経営安定対策、生産者間の不公平感の確保が欠かせない」と指摘した。一方で非系統の最大生乳集荷・卸業者MMJの藤本涼子氏は「自主流通の事業者も脱粉対策での拠出金を負担すべきとの意見があるが、自主流通の余乳を加工に回すなど最大限引き受けている」と反論している。
こうした中で、中酪要請の柱の一つが非系統の自主流通業者も含めた全国的な生乳需給調整の枠組み構築だ。これには脱粉対策のようにJミルクなどの民間主導では具体化が難しい。あくまで政府主導で、加工原料乳補給金制度に参加する関係者を網羅する形での多目的基金創設などの提案なども検討すべきとの指摘もある。畜産部会で全参加型の需給調整構築の議論を深めるべきだ。
牛乳価格下げ圧力に懸念
中酪は、要請の中で国内酪農の状況をコスト高止まりで厳しい経営環境を続いていると訴えた。指定生乳生産者団体傘下の受託農家は高水準での減少が続く。ここで「指定団体外の自主生乳流通量の拡大が、指定団体への需給調整リスク・コストの偏在化や小売価格の引き下げ圧力の増加、適正な価格形成への阻害要因ともなっている」と改正畜安法の問題点を具体的に指摘したことが重要だ。
特に注目したいのは「小売価格の引き下げ圧力の増加」。つまり数度の飲用乳価引き上げで、牛乳小売価格が上がったものの、下げ圧力が増しているというのだ。19日発表の最新のJミルク需給短信を見ると牛乳販売単価は1000cc当たり225・6円。だが、これはあくまで平均価格。改正畜安法に伴う生乳流通自由化で現在、スーパー店頭価格は同じ牛乳でありながら250円以上の牛乳と200円以下に両極化している。
指定団体経由の生乳を原料とした大手乳業のNB(ナショナルブランド)牛乳と系統外の割安な原乳を使用した中小乳業との価格差と言っていい。先のJミルク225円は大手NB牛乳260円と系統外生乳使用の190円の平均価格に匹敵する。ブランド力もあるが、食品価格の相次ぐ値上げの中で価格の安い牛乳に消費者の手が伸びるのは止められないだろう。結果、販売を落とさないためにも、週末特売などで大手NB牛乳も徐々に牛乳納入価格の値下げを余儀なくされる傾向にある。
一見、牛乳価格市場での販売競争に見えるが、この状況が続けばしわ寄せは生産現場に及ぶ。乳業メーカーの飲用乳価引き上げ余力がなくなり、いくら酪農家がコストの乳価反映を求めても、乳業が応じなくなりかねない。それは「適正な価格形成の阻害要因」とも結びつく。規制緩和を突き詰めた改正畜安法が、いま政策的課題になっている価格形成に悪影響を及ぼす〈政策矛盾〉に陥っている。その具体的是正措置が急がれる。
(次回「透視眼」は2025年1月号)
(次回「透視眼」は2025年1月号)
- 2025年 12月号
- 2025年 10月号
- 2025年 8月号
- 2025年 6月号
- 2025年 4月号
- 2025年 2月号
- 2025年 1月号
- 2024年 10月号
- 2024年 9月号
- 2024年 8月号
- 2024年 6月号
- 2024年 4月号
- 2024年 2月号
- 2024年 1月号
- 2023年 12月号
- 2023年 10月号
- 2023年 8月号
- 2023年 6月号
- 2023年 4月号
- 2023年 2月号
- 2023年 1月号
- 2022年 12月号
- 2022年 10月号
- 2022年 8月号
- 2022年 6月号
- 2022年 4月号
- 2022年 2月号
- 2022年 1月号
- 2021年 12月号
- 2021年 10月号
- 2021年 8月号
- 2021年 6月号
- 2021年 4月号
- 2021年 2月号
- 2021年 1月号
- 2020年 12月号
- 2020年 10月号
- 2020年 8月号
- 2020年 6月号
- 2020年 4月号
- 2020年 2月号
- 2020年 1月号
- 2019年 12月号
- 2019年 10月号
- 2019年 8月号
- 2019年 6月号
- 2019年 4月号
- 2019年 2月号
- 2019年 1月号
- 2018年 12月号
- 2018年 10月号
- 2018年 8月号
- 2018年 6月号
- 2018年 4月号
- 2018年 2月号
- 2018年 1月号
- 2017年 12月号
- 2017年 10月号
- 2017年 8月号
- 2017年 6月号
- 2017年 4月号
- 2017年 2月号
- 2017年 1月号
- 2016年 12月号
- 2016年 10月号
- 2016年 8月号
- 2016年 6月号
- 2016年 4月号
- 2016年 2月号
- 2016年 1月号