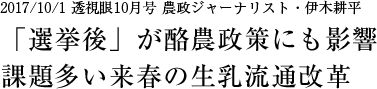
突然の解散・総選挙である。10月22日投開票の結果がどうなるか。それによっては、今年吹き荒れた農協改革、酪農改革も「風向き」が変わるかもしれない。選挙後の「政局」から目が離せない。一方で、農業自由化の荒波は連綿と押し寄せる。農水省は、生乳流通改革の政省令で加工向け月平均の最低2割を条件に補給金交付要件を整えるなどしたが、指定生乳生産者団体の役割維持の先行きは不透明なままだ。国内農業・酪農を守る業界挙げての「防波堤」構築が急務だ。
10月22日「敵前逃亡解散」とも
解散、総選挙はいつなのか。政治にとり最大関心時だった。「安倍1強体制」にほころびが見える中で、政権の行方を左右し命運を握る10月の衆院トリプル補選が迫っていたが、それを呑み込む形で10月22日に衆院選投開票となる。選挙戦を通じ、与野党とも経済対策とともに地方対策、農政対策の具体化が問われる。農業団体の間では「安倍一強」下で誰も望んでいない農協改革や指定団体改革を強行されたとの思いも強い。ここは自民党にお灸をすえる意味でもある程度の自民減、野党健闘の形を作りたいとの思いもある。だが問題は「選挙後」だ。手負いとなった自民党は必ず巻き返しに出る。ここは、行き過ぎた規制改革にブレーキをかけながら、農業団体の意向を反映にした公約づくりに反映させ、今後の持続可能な農業の礎を強固にしなければならない。それにしても臨時国会冒頭解散とは、森友・加計問題の疑惑にふたをし、新大臣に全く答弁させない「敵前逃亡解散」と批判されてもやむを得まい。選挙結果の詳細な分析は次号に譲るとしても、これまでの盤石な政権基盤とは様変わりするのは間違いない。
安倍首相と自民党幹部が最も気にする数字は2つある。465議席の3分の2を占める「310」と、過半数の233。310は安倍首相の執念である憲法改正の発議に必要な数字だ。233は法案可決に必要な過半数の水準である。
解散、総選挙の時期で関係者の見方は、年内から1年後の来秋まで大きく分かれていた。解散日程を大きく左右する日にちは二つあった。トリプル補選を予定していた10月22日と、衆院議員の任期満了となる来年12月13日である。今年12月中旬には衆院議員の残された任期は1年を切る。これまでを振り返ると、衆院選は平均2年半で打ってきた。
首相の衆院解散権は権力の源泉で、政権の求心力とも重なってきた。しかし、任期満了が近づくほど「追い込まれ解散」の色彩が濃くなる。2009年、麻生内閣は任期切れ間際の解散・総選挙で惨敗し民主党に政権を奪われ野に下った。
これまで安倍晋三首相の悲願だった憲法改正の動向を踏まえ、現状の3分の2の改憲勢力を維持するため、1年後の来秋との見通しが多かった。だが、東京都議選の自民党の大敗北に加え、小池百合子都知事の影響を受けた非自民結集の新党結成の動き、10月22日の衆院3補選が迫る中で、早期に総選挙に打って出るのではないかとの憶測が広がっていた。総選挙が早いほど自民との負け幅は小さくなるとの見立てもある。
直近の政治判断材料は三つ。
最大の問題は巨大与党・自公政権に立ち向かうには、弱小連合とはいえ野党が束になり戦う他ない。いったい民共を柱とした「野党共闘」が果たして機能するのかどうか。
保守分裂となった8月下旬の茨城県知事選。自公推薦の新人候補が現職を約7万票の差をつけ当選した。自民党はこれまで、地方選で東京都議選と仙台市長選で連敗していただけに与党内には安どの声が出ている。だが、内実を見ると与党内に「逆風はまだ収まっていない」との声も出ている。実態を見れば、無党派層の支持が自民党から離れたままだ。安倍政権への根強い政治不信が一向に消えていないと見るべきだろう。与党幹部が相次いで応援に駆け付け国政選挙並みの総力戦で闘った半面、現職知事の多選批判に加え民進党は自主投票に回った結果の勝利に過ぎない。さらに9月には、最大野党・民進党の新代表が前原誠司氏に決まり新体制が整った。だが、党勢はいまだに回復しない。最近の世論調査でも支持率は消費税並みの一桁にとどまる。三つ目は小池都知事率いる「希望の党」の動き。さて、どうなるか。総選挙の結果次第では自民党内の「安倍おろし」も始まりかねない。その際の「ポスト安倍」の筆頭は岸田政調会長、次に石破元幹事長だろう。いまだに岸田禅譲説の絶えないだけに、「選挙後」の政局の行方は予断を許さない。
安倍首相と自民党幹部が最も気にする数字は2つある。465議席の3分の2を占める「310」と、過半数の233。310は安倍首相の執念である憲法改正の発議に必要な数字だ。233は法案可決に必要な過半数の水準である。
解散、総選挙の時期で関係者の見方は、年内から1年後の来秋まで大きく分かれていた。解散日程を大きく左右する日にちは二つあった。トリプル補選を予定していた10月22日と、衆院議員の任期満了となる来年12月13日である。今年12月中旬には衆院議員の残された任期は1年を切る。これまでを振り返ると、衆院選は平均2年半で打ってきた。
首相の衆院解散権は権力の源泉で、政権の求心力とも重なってきた。しかし、任期満了が近づくほど「追い込まれ解散」の色彩が濃くなる。2009年、麻生内閣は任期切れ間際の解散・総選挙で惨敗し民主党に政権を奪われ野に下った。
これまで安倍晋三首相の悲願だった憲法改正の動向を踏まえ、現状の3分の2の改憲勢力を維持するため、1年後の来秋との見通しが多かった。だが、東京都議選の自民党の大敗北に加え、小池百合子都知事の影響を受けた非自民結集の新党結成の動き、10月22日の衆院3補選が迫る中で、早期に総選挙に打って出るのではないかとの憶測が広がっていた。総選挙が早いほど自民との負け幅は小さくなるとの見立てもある。
直近の政治判断材料は三つ。
最大の問題は巨大与党・自公政権に立ち向かうには、弱小連合とはいえ野党が束になり戦う他ない。いったい民共を柱とした「野党共闘」が果たして機能するのかどうか。
保守分裂となった8月下旬の茨城県知事選。自公推薦の新人候補が現職を約7万票の差をつけ当選した。自民党はこれまで、地方選で東京都議選と仙台市長選で連敗していただけに与党内には安どの声が出ている。だが、内実を見ると与党内に「逆風はまだ収まっていない」との声も出ている。実態を見れば、無党派層の支持が自民党から離れたままだ。安倍政権への根強い政治不信が一向に消えていないと見るべきだろう。与党幹部が相次いで応援に駆け付け国政選挙並みの総力戦で闘った半面、現職知事の多選批判に加え民進党は自主投票に回った結果の勝利に過ぎない。さらに9月には、最大野党・民進党の新代表が前原誠司氏に決まり新体制が整った。だが、党勢はいまだに回復しない。最近の世論調査でも支持率は消費税並みの一桁にとどまる。三つ目は小池都知事率いる「希望の党」の動き。さて、どうなるか。総選挙の結果次第では自民党内の「安倍おろし」も始まりかねない。その際の「ポスト安倍」の筆頭は岸田政調会長、次に石破元幹事長だろう。いまだに岸田禅譲説の絶えないだけに、「選挙後」の政局の行方は予断を許さない。
トランプ主導の日米交渉
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉が始まった。「自国第一主義」を掲げるトランプ米政権による通商政策見直しの一環だ。今後、米韓FTA再協議も実施される。トランプ大統領は2国間協議シフトを鮮明にしており、安全保障問題も絡めながら日米協議を迫ってくる可能性が強い。NAFTA再交渉の行方を注視したい。
今回のNAFTA再交渉が持つ意味は大きい。トランプ政権が取り組む最初の貿易交渉だからだ。キーワードは貿易赤字の削減である。その行方は、日米経済対話や米国を除く11カ国での環太平洋連携協定(TPP)発効を目指すTPP11にも大きな影響を及ぼす。再交渉は迅速に進み来年前半で終えるとの見方も出ている。
NAFTA見直しは大統領選公約の一つ。公約実現が一向に進まない中で、通商交渉で具体的な成果を挙げ、政権の支持率を上げようとの思惑がある。通商面では既にTPP離脱を表明した。トランプ氏の念頭にあるのは来年11月の米中間選挙だ。ここで与党・共和党が敗北すれば、政権の求心力を一挙に失いかねない。「自国第一主義」を掲げ、特に製造業復活を前面に出し労働者の支持を得た。それだけに、再交渉の開催地を当初、「ラストベルト」(さびれた工業地帯)と呼ばれる一つ、鉄鋼業の象徴だったピッツバーグとしようとしたのは政治的な意味合いが強い。農業分野では品目によって3カ国の利害が入り乱れる。米通商代表部(USTR)は残る関税の削減・撤廃で米国産農産物の市場拡大を目指す方針を表明した。特に、カナダの酪農製品の保護削減も大きな焦点となる。
次に、5年半前に発効した米韓FTA再交渉が控える。米国は激動する朝鮮半島情勢なども踏まえ、主食の米で韓国に一定の配慮を行った。米韓協定は国家の主権侵害となりかねない投資家・国家紛争処理(ISD)条項をはじめ、米国仕様のルール化や大幅な規制緩和などが盛り込まれ、TPPの原型、「ミニTPP」とされた。再交渉で韓国農業は一層の市場開放を迫られるのは間違いない。
NAFTA再交渉での乳製品見直しの行方や、その後の米韓協定再交渉での米の扱いなどで、米国はどういった強硬手段を取るのか。注視したいのは、トランプ政権が対中圧力で、制裁措置を行う米通商法301条をちらつかせていることだ。
慶応大学の金子勝教授は、トランプ政権が日米2国間貿易交渉を要求してくるのは時間の問題だと指定。その上で一層の農産物自由化要求に「安倍政権がとても踏み応えられるとは思えない」と懸念を表明している。日本は既に食料自給率38%と先進国最低の実態を改めて思う。安倍政権が理不尽な対日要求をはねつけなければ、国内農業者の政治不信は頂点に達する。
今回のNAFTA再交渉が持つ意味は大きい。トランプ政権が取り組む最初の貿易交渉だからだ。キーワードは貿易赤字の削減である。その行方は、日米経済対話や米国を除く11カ国での環太平洋連携協定(TPP)発効を目指すTPP11にも大きな影響を及ぼす。再交渉は迅速に進み来年前半で終えるとの見方も出ている。
NAFTA見直しは大統領選公約の一つ。公約実現が一向に進まない中で、通商交渉で具体的な成果を挙げ、政権の支持率を上げようとの思惑がある。通商面では既にTPP離脱を表明した。トランプ氏の念頭にあるのは来年11月の米中間選挙だ。ここで与党・共和党が敗北すれば、政権の求心力を一挙に失いかねない。「自国第一主義」を掲げ、特に製造業復活を前面に出し労働者の支持を得た。それだけに、再交渉の開催地を当初、「ラストベルト」(さびれた工業地帯)と呼ばれる一つ、鉄鋼業の象徴だったピッツバーグとしようとしたのは政治的な意味合いが強い。農業分野では品目によって3カ国の利害が入り乱れる。米通商代表部(USTR)は残る関税の削減・撤廃で米国産農産物の市場拡大を目指す方針を表明した。特に、カナダの酪農製品の保護削減も大きな焦点となる。
次に、5年半前に発効した米韓FTA再交渉が控える。米国は激動する朝鮮半島情勢なども踏まえ、主食の米で韓国に一定の配慮を行った。米韓協定は国家の主権侵害となりかねない投資家・国家紛争処理(ISD)条項をはじめ、米国仕様のルール化や大幅な規制緩和などが盛り込まれ、TPPの原型、「ミニTPP」とされた。再交渉で韓国農業は一層の市場開放を迫られるのは間違いない。
NAFTA再交渉での乳製品見直しの行方や、その後の米韓協定再交渉での米の扱いなどで、米国はどういった強硬手段を取るのか。注視したいのは、トランプ政権が対中圧力で、制裁措置を行う米通商法301条をちらつかせていることだ。
慶応大学の金子勝教授は、トランプ政権が日米2国間貿易交渉を要求してくるのは時間の問題だと指定。その上で一層の農産物自由化要求に「安倍政権がとても踏み応えられるとは思えない」と懸念を表明している。日本は既に食料自給率38%と先進国最低の実態を改めて思う。安倍政権が理不尽な対日要求をはねつけなければ、国内農業者の政治不信は頂点に達する。
大手乳業100年と生乳流通改革
国内の酪農・乳業は経験のない「大変革期」を迎えている。大手乳業メーカー設立から100年。生乳需給安定に大きな役割を果たしてきた酪農不足払い制度も抜本的に見直す一方で、貿易自由化が進む。加速する自由化、安定供給、制度・政策の三つのリスクにどう対応するのか。乳の価値向上を進めると共に、喫緊の課題は関係者挙げた酪農生産基盤の維持・強化だ。
「三大リスク」が今、酪農・乳業界を大きく揺るがす。特に自由化リスクへの対応は待ったなしだ。環太平洋連携協定(TPP)に続き、酪農先進地で高付加価値チーズに圧倒的な強みを持つ欧州連合(EU)との通商交渉で大枠合意となった。EUとは、TPPで除外したソフト系チーズにまで自由化が波及した。国挙げて国産チーズ振興を進め、大手乳業も施設増設をしてきた。6次産業化で各地で創意工夫ある手作りのチーズ工房も増えている。こうした中での乳製品自由化の拡大だ。
国は国産チーズ振興をどうするのか。具体的な支援策が欠かせない。こうした中で、乳業も対応を急ピッチで進める。北海道東部・標茶町にある雪印メグミルクの基幹工場・磯分内工場の建て直しは典型だ。バター、脱脂粉乳に加え、輸入品対抗で液状乳製品の生クリームや脱脂濃縮乳の供給体制を拡充する。
乳業の歴史を振り返ると、3大乳業メーカーのうち森永乳業は9月に創業100年を迎えた。明治は昨年100周年。雪メグは少し遅れ1925年に北海道で立ち上がった。関東大震災を経て乳製品の輸入急増から国内相場が暴落。生産者相互の共販のため酪農団体が前身という点で、先の2メーカーとは性格が大きく異なる。こうした中で、現在に至る大手乳業と国内酪農の発展は1世紀の時を経て大きな転換点を迎えた。
概観すると、酪農・乳業はこの100年を前後して50年単位で歴史的な節目を迎えている。ほぼ150年前の明治初め、政府は乳牛を大量に輸入し国内で酪農振興に着手。都市部を中心に乳牛を飼い牛乳を販売する搾乳業者が拡大していく。食の洋風化も進む大正期に入り、保存できる練乳などの本格生産を目指し、明治、森永が創業した。いずれも母体は練乳を使ったキャラメル製造など製菓会社で、やがて乳業部門が独立していく。宮原道夫森永乳業社長は「ちょうど100年前は練乳の安定供給と都市近郊の酪農の発展が重なった」と話す。
いま一つのリスクは制度・政策である。
半世紀前には暫定措置法としての酪農不足払い制度ができる。指定生乳生産者団体を通じ酪農家に加工原料乳補給金を支給する仕組みで、生乳の一元集荷・多元販売が実現した。生乳需給調整・安定供給と乳質向上が担保された。特に、加工原料乳地帯の北海道の酪農振興に大きく貢献した。同時に飲用乳中心の都府県との「すみ分け」が可能となる。酪農家同士による牛乳価格競争となる南北戦争を防ぎ、国内の酪農家の共存共栄へ効力を発揮してきた。それが規制緩和の荒波の中で、改正畜産経営安定法制定に伴い来春から指定団体の一元集荷から生乳販売の複線化に大転換する。加工原料乳の出荷割合の最低ラインを2割とするなど「いいとこ取り」を防ぐ政省令をまとめたが、需給調整機能はどうなるのか先行きはまだ不透明だ。酪農家の所得維持の観点からも、政策運用面での政府の責任は重い。
最大のリスクは国内酪農の生乳安定供給が今後どうなるかだ。自由化の進展と酪農制度の抜本見直しは、酪農家の先行き不安を募らせている。それを解消するのは政治の責任も大きい。世界人口が拡大を続け、新興国の乳製品需要が増える中で、輸入品に頼る時代ではない。トランプ米政権の自国主義や地域紛争で為替変動の先行きも読めない。
「三大リスク」が今、酪農・乳業界を大きく揺るがす。特に自由化リスクへの対応は待ったなしだ。環太平洋連携協定(TPP)に続き、酪農先進地で高付加価値チーズに圧倒的な強みを持つ欧州連合(EU)との通商交渉で大枠合意となった。EUとは、TPPで除外したソフト系チーズにまで自由化が波及した。国挙げて国産チーズ振興を進め、大手乳業も施設増設をしてきた。6次産業化で各地で創意工夫ある手作りのチーズ工房も増えている。こうした中での乳製品自由化の拡大だ。
国は国産チーズ振興をどうするのか。具体的な支援策が欠かせない。こうした中で、乳業も対応を急ピッチで進める。北海道東部・標茶町にある雪印メグミルクの基幹工場・磯分内工場の建て直しは典型だ。バター、脱脂粉乳に加え、輸入品対抗で液状乳製品の生クリームや脱脂濃縮乳の供給体制を拡充する。
乳業の歴史を振り返ると、3大乳業メーカーのうち森永乳業は9月に創業100年を迎えた。明治は昨年100周年。雪メグは少し遅れ1925年に北海道で立ち上がった。関東大震災を経て乳製品の輸入急増から国内相場が暴落。生産者相互の共販のため酪農団体が前身という点で、先の2メーカーとは性格が大きく異なる。こうした中で、現在に至る大手乳業と国内酪農の発展は1世紀の時を経て大きな転換点を迎えた。
概観すると、酪農・乳業はこの100年を前後して50年単位で歴史的な節目を迎えている。ほぼ150年前の明治初め、政府は乳牛を大量に輸入し国内で酪農振興に着手。都市部を中心に乳牛を飼い牛乳を販売する搾乳業者が拡大していく。食の洋風化も進む大正期に入り、保存できる練乳などの本格生産を目指し、明治、森永が創業した。いずれも母体は練乳を使ったキャラメル製造など製菓会社で、やがて乳業部門が独立していく。宮原道夫森永乳業社長は「ちょうど100年前は練乳の安定供給と都市近郊の酪農の発展が重なった」と話す。
いま一つのリスクは制度・政策である。
半世紀前には暫定措置法としての酪農不足払い制度ができる。指定生乳生産者団体を通じ酪農家に加工原料乳補給金を支給する仕組みで、生乳の一元集荷・多元販売が実現した。生乳需給調整・安定供給と乳質向上が担保された。特に、加工原料乳地帯の北海道の酪農振興に大きく貢献した。同時に飲用乳中心の都府県との「すみ分け」が可能となる。酪農家同士による牛乳価格競争となる南北戦争を防ぎ、国内の酪農家の共存共栄へ効力を発揮してきた。それが規制緩和の荒波の中で、改正畜産経営安定法制定に伴い来春から指定団体の一元集荷から生乳販売の複線化に大転換する。加工原料乳の出荷割合の最低ラインを2割とするなど「いいとこ取り」を防ぐ政省令をまとめたが、需給調整機能はどうなるのか先行きはまだ不透明だ。酪農家の所得維持の観点からも、政策運用面での政府の責任は重い。
最大のリスクは国内酪農の生乳安定供給が今後どうなるかだ。自由化の進展と酪農制度の抜本見直しは、酪農家の先行き不安を募らせている。それを解消するのは政治の責任も大きい。世界人口が拡大を続け、新興国の乳製品需要が増える中で、輸入品に頼る時代ではない。トランプ米政権の自国主義や地域紛争で為替変動の先行きも読めない。
アジアの成長とASEAN半世紀
東南アジア諸国連合(ASEAN)が創設50年の節目を迎えた。半世紀の歩みは地域内の結束強化の一方で、大国の政治、経済主導権争いと重なる。日米中の経済3大国にとっても、ASEANの扱いは今後の通商交渉の鍵を握る。ASEANの開かれた地域主義の一方で各国の多様性の維持である。こうした基本理念を土台に、今後の地域統合に向かうべきだ。
創設から半世紀を経て、今ほどその存在意義を問われている時はない。グローバル化と、その反動としての保護主義の台頭。揺れ動く朝鮮半島情勢、アジア太平洋を巡る米中経済覇権争いの大波はASEANにも押し寄せているからだ。マニラでのASEAN地域フォーラム(ARF)でも、北朝鮮の核・ミサイル開発問題での制裁措置で日米と中露の意見対立が鮮明となった。そんな世界的な政治の地殻変動の中にASEANは位置付く。
今後の焦点は、ASEANを舞台とした2つのメガ自由貿易協定(FTA)とされる広域通商交渉の行方だ。大きな異変はトランプ米政権の登場で、TPP離脱を決めたことだ。
まずは環太平洋連携協定(TPP)。そして東アジア地域包括的経済連携協定(RCEP)。ASEAN10カ国のうちTPPには4カ国、RCEPには全加盟国が入る。いずれにしても二つのメガFTAは、東南アジアの成長力を取り込むためASEANが大きな土台で成り立つ。TPPは米国主導で中国は外れている。中国包囲網と称された理由だ。だが米国離脱で今はTPP11で具体的な議論が進む。一方で、RCEPは中国とインドが加わり米国は入っていない。日本はどちらにも入る。 日本はどう対応するのか。安倍晋三首相は国会で「TPP協定合意は今後の経済連携の礎となる」と繰り返し、RCEPでも「野心的な協定となるよう交渉をリードしたい」と強調。こうした中で、今夏にはEUと乳製品の一部でTPPの内容を上回る大枠合意をした。TPP基準の通商路線は結局、農産物の一層の自由化を進めることを裏付けた。このままでは国内農業は衰退の一途をたどりかねない。
ASEAN創設50年を迎え、今後、その全加盟国が入るRCEPの協議は大詰めを迎える。米を主食とする国々も多い。日本が「TPP基準」をごり押しすれば、米を巡り激しい対立が起きるのは間違いない。多様性と調和に基づいた柔軟な交渉、国内外の農業分野もウインウインとなる交渉に転換すべきだ。
(次回「透視眼」は12月号)
創設から半世紀を経て、今ほどその存在意義を問われている時はない。グローバル化と、その反動としての保護主義の台頭。揺れ動く朝鮮半島情勢、アジア太平洋を巡る米中経済覇権争いの大波はASEANにも押し寄せているからだ。マニラでのASEAN地域フォーラム(ARF)でも、北朝鮮の核・ミサイル開発問題での制裁措置で日米と中露の意見対立が鮮明となった。そんな世界的な政治の地殻変動の中にASEANは位置付く。
今後の焦点は、ASEANを舞台とした2つのメガ自由貿易協定(FTA)とされる広域通商交渉の行方だ。大きな異変はトランプ米政権の登場で、TPP離脱を決めたことだ。
まずは環太平洋連携協定(TPP)。そして東アジア地域包括的経済連携協定(RCEP)。ASEAN10カ国のうちTPPには4カ国、RCEPには全加盟国が入る。いずれにしても二つのメガFTAは、東南アジアの成長力を取り込むためASEANが大きな土台で成り立つ。TPPは米国主導で中国は外れている。中国包囲網と称された理由だ。だが米国離脱で今はTPP11で具体的な議論が進む。一方で、RCEPは中国とインドが加わり米国は入っていない。日本はどちらにも入る。 日本はどう対応するのか。安倍晋三首相は国会で「TPP協定合意は今後の経済連携の礎となる」と繰り返し、RCEPでも「野心的な協定となるよう交渉をリードしたい」と強調。こうした中で、今夏にはEUと乳製品の一部でTPPの内容を上回る大枠合意をした。TPP基準の通商路線は結局、農産物の一層の自由化を進めることを裏付けた。このままでは国内農業は衰退の一途をたどりかねない。
ASEAN創設50年を迎え、今後、その全加盟国が入るRCEPの協議は大詰めを迎える。米を主食とする国々も多い。日本が「TPP基準」をごり押しすれば、米を巡り激しい対立が起きるのは間違いない。多様性と調和に基づいた柔軟な交渉、国内外の農業分野もウインウインとなる交渉に転換すべきだ。
(次回「透視眼」は12月号)
- 2026年 2月号
- 2026年 1月号
- 2025年 12月号
- 2025年 10月号
- 2025年 8月号
- 2025年 6月号
- 2025年 4月号
- 2025年 2月号
- 2025年 1月号
- 2024年 10月号
- 2024年 9月号
- 2024年 8月号
- 2024年 6月号
- 2024年 4月号
- 2024年 2月号
- 2024年 1月号
- 2023年 12月号
- 2023年 10月号
- 2023年 8月号
- 2023年 6月号
- 2023年 4月号
- 2023年 2月号
- 2023年 1月号
- 2022年 12月号
- 2022年 10月号
- 2022年 8月号
- 2022年 6月号
- 2022年 4月号
- 2022年 2月号
- 2022年 1月号
- 2021年 12月号
- 2021年 10月号
- 2021年 8月号
- 2021年 6月号
- 2021年 4月号
- 2021年 2月号
- 2021年 1月号
- 2020年 12月号
- 2020年 10月号
- 2020年 8月号
- 2020年 6月号
- 2020年 4月号
- 2020年 2月号
- 2020年 1月号
- 2019年 12月号
- 2019年 10月号
- 2019年 8月号
- 2019年 6月号
- 2019年 4月号
- 2019年 2月号
- 2019年 1月号
- 2018年 12月号
- 2018年 10月号
- 2018年 8月号
- 2018年 6月号
- 2018年 4月号
- 2018年 2月号
- 2018年 1月号
- 2017年 12月号
- 2017年 10月号
- 2017年 8月号
- 2017年 6月号
- 2017年 4月号
- 2017年 2月号
- 2017年 1月号
- 2016年 12月号
- 2016年 10月号
- 2016年 8月号
- 2016年 6月号
- 2016年 4月号
- 2016年 2月号
- 2016年 1月号


