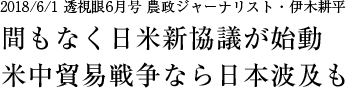
改正畜安法や国が米の生産調整から手を引くなど、農政が大きく転換する中で、今年の農業白書はこうした「危機的」な側面を直視せず、むしろ「楽観論」に終始した。一方で、トランプ台風は衰えを知らず、2大経済大国・米中の貿易戦争リスクが一段と高まってきた。輸入制限など相互の報復合戦が広がれば、米国産大豆や食肉など日本農業への影響も懸念される事態を招く。早ければ6月下旬には通商問題などで日米新協議もは始まる。一層の農業自由化に結び付かないか、トランプ政権の対応から目が離せない。
「楽観論」に終始した農業白書
農水省は食料・農業・農村政策審議会企画部会で今年の食料・農業・農村白書を決め、閣議決定した。特集で若手農業者の動向など明るい側面を詳述した。問題は先進国最低の食料自給率をはじめ国内農業への危機感が薄いことだ。国内生産を大前提にした食料安全保障の確立と自給率引き上げの道程をもっと前面に出すべきだったが、「楽観論」に終始したと言わざるを得ない。 企画部会では、複数の出席委員から課題とされたのが自給率の記述のありようだ。国是であり農政上の重要な柱の一つでもある自給率引き上げへの強い決意が感じられないのは大きな問題である。同省は問題点を受け止め、自給率向上のより具体的な書き込みを行うべきだろう。
特集の他、4章で構成されている。第1章のテーマが「食料の安定供給の確保」で、自給率などを取り上げている。先の企画部会で農業団体からはカロリーベースで45パーセント目標と実現への道筋を明記するように強く要請。東京大学大学院の中嶋康博教授は「なぜ38パーセントに留まっているのかが記述されるのかどうか」と指摘。45パーセント目標の実現に向けた課題を分析し、白書で明確化するよう求めた。
さらに、当初の白書骨子案で総合的な食料安全保障の確立の記述で「輸入農産物の安定供給を確保するための取り組みが重要」との表現が、輸入で賄って食料安保を確立する誤ったイメージを持たれかねないとの批判も出た。あくまで大前提は、国内農業生産を増大し自給率引き上げと連動しながら、食料安保を確立する道筋を明確に示すべきで、この部分は書き直された
5年に一度の食料・農業・農村基本計画の見直しの時期が迫る。自給率を引き上げるため、国産を大前提にした日本型食料安保の在り方、基本政策確立に向けた具体的な論議に着手する。今回の白書でも、こうした農政上の課題をしっかり受け止めた対応が問われていた。
農業白書が「楽観論」に終始しているのは、安倍晋三首相が1月下旬の通常国会冒頭の施政方針演説で触れた「農林水産新時代」の記述も影響しているのではないか。
首相は、農林水産物の輸出拡大や生産農業所得増、若手新規就農者の増加などは政権が旗を振る「攻めの農政」の帰結だとして、農政改革の加速するとした。安倍政権が5年半と長期化する中で、規制改革推進会議の意向が農政改革に色濃く反映されるなど、官邸主導の政策実施が進む。いわば「忖度農政」の弊害を、今回の農業白書も投影しているのかもしれない。
特集の他、4章で構成されている。第1章のテーマが「食料の安定供給の確保」で、自給率などを取り上げている。先の企画部会で農業団体からはカロリーベースで45パーセント目標と実現への道筋を明記するように強く要請。東京大学大学院の中嶋康博教授は「なぜ38パーセントに留まっているのかが記述されるのかどうか」と指摘。45パーセント目標の実現に向けた課題を分析し、白書で明確化するよう求めた。
さらに、当初の白書骨子案で総合的な食料安全保障の確立の記述で「輸入農産物の安定供給を確保するための取り組みが重要」との表現が、輸入で賄って食料安保を確立する誤ったイメージを持たれかねないとの批判も出た。あくまで大前提は、国内農業生産を増大し自給率引き上げと連動しながら、食料安保を確立する道筋を明確に示すべきで、この部分は書き直された
5年に一度の食料・農業・農村基本計画の見直しの時期が迫る。自給率を引き上げるため、国産を大前提にした日本型食料安保の在り方、基本政策確立に向けた具体的な論議に着手する。今回の白書でも、こうした農政上の課題をしっかり受け止めた対応が問われていた。
農業白書が「楽観論」に終始しているのは、安倍晋三首相が1月下旬の通常国会冒頭の施政方針演説で触れた「農林水産新時代」の記述も影響しているのではないか。
首相は、農林水産物の輸出拡大や生産農業所得増、若手新規就農者の増加などは政権が旗を振る「攻めの農政」の帰結だとして、農政改革の加速するとした。安倍政権が5年半と長期化する中で、規制改革推進会議の意向が農政改革に色濃く反映されるなど、官邸主導の政策実施が進む。いわば「忖度農政」の弊害を、今回の農業白書も投影しているのかもしれない。
米中間選挙まで半年切る
11月6日の米議会中間選挙まで半年を切った。与党・共和党の苦戦が予想される中で、トランプ政権は一段と「米国第一」を前面に出し貿易戦争リスクが高まる。大きな懸念は、日米新協議の中で米政権が「安保カード」を駆使した通商攻勢の恐れだ。これまで以上に農業への対日圧力に備えを強めねばならない。
トランプ政権は、一定の期限を区切りながら貿易赤字削減に的を絞り、各国に政治・経済的な圧力をかけ続けている。米中間選挙まで半年を切る中で、自国最優先の具体的な成果を有権者に示すためだ。
今後のトランプ大統領の通商交渉を占う動きを、急転する朝鮮半島情勢や激化する米中貿易紛争も絡め読み解きたい。
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉の閣僚協議が5月上に再開した。最大焦点の自動車の「原産地規制」見直しで、関税ゼロの際の部品の域内調達率大幅引き上げなどを挙げ米国内の雇用拡大につながる主張を繰り返した。ここで注目すべき動きは、米国、カナダ、メキシコの3カ国で、早期決着の機運が高まってきたと伝えられていることだ。
政治日程は7月にメキシコ大統領選、そして最大焦点の11月の米中間選挙を迎える。米通商代表部(USTR)のライトハイザー代表が合意を急ぐのは、新たなNAFTA協定を与党が多数を占める現行の議会で承認してもらいたいからだ。与党の苦戦が予想される中で、来年1月以降の新議会で新協定の賛成を得られなくことを危惧している。通商交渉が、政権運営の今後を左右する中間選挙を念頭に、より速度を上げながら進みだすと見た方がいい。
米議会の現状は、上院(定数100)が共和党51、民主党49。定数435の下院は共和党が過半数218を19議席上回る。上下院とも与党が多数を占める状況だ。だが、政権1期目の中間選挙は、大統領選の「逆ばね」で大敗するケースが多い。
上院は与野党差わずか2議席だが、今回の改選対象35議席のうち26議席は民主党が占め、過半数奪取は難しいとの見方が強い。焦点は事実上、現職大統領の信任を問う全議席改選となる下院の行方だ。民主党支持者は都市部に集中する半面、共和党は農村部の大規模農業者や地方にも支持者が分散する。今後、劣勢を跳ね返すためにも、トランプ氏の支持が強い中間層や製造業の労働者、大規模農業者などの意向を反映した政治行動が強まる可能性が強い。
トランプ政権は、一定の期限を区切りながら貿易赤字削減に的を絞り、各国に政治・経済的な圧力をかけ続けている。米中間選挙まで半年を切る中で、自国最優先の具体的な成果を有権者に示すためだ。
今後のトランプ大統領の通商交渉を占う動きを、急転する朝鮮半島情勢や激化する米中貿易紛争も絡め読み解きたい。
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉の閣僚協議が5月上に再開した。最大焦点の自動車の「原産地規制」見直しで、関税ゼロの際の部品の域内調達率大幅引き上げなどを挙げ米国内の雇用拡大につながる主張を繰り返した。ここで注目すべき動きは、米国、カナダ、メキシコの3カ国で、早期決着の機運が高まってきたと伝えられていることだ。
政治日程は7月にメキシコ大統領選、そして最大焦点の11月の米中間選挙を迎える。米通商代表部(USTR)のライトハイザー代表が合意を急ぐのは、新たなNAFTA協定を与党が多数を占める現行の議会で承認してもらいたいからだ。与党の苦戦が予想される中で、来年1月以降の新議会で新協定の賛成を得られなくことを危惧している。通商交渉が、政権運営の今後を左右する中間選挙を念頭に、より速度を上げながら進みだすと見た方がいい。
米議会の現状は、上院(定数100)が共和党51、民主党49。定数435の下院は共和党が過半数218を19議席上回る。上下院とも与党が多数を占める状況だ。だが、政権1期目の中間選挙は、大統領選の「逆ばね」で大敗するケースが多い。
上院は与野党差わずか2議席だが、今回の改選対象35議席のうち26議席は民主党が占め、過半数奪取は難しいとの見方が強い。焦点は事実上、現職大統領の信任を問う全議席改選となる下院の行方だ。民主党支持者は都市部に集中する半面、共和党は農村部の大規模農業者や地方にも支持者が分散する。今後、劣勢を跳ね返すためにも、トランプ氏の支持が強い中間層や製造業の労働者、大規模農業者などの意向を反映した政治行動が強まる可能性が強い。
指定団体700万トン割れ
2017年度の指定生乳生産者団体の生乳生産量が30年ぶりに700万トン(受託乳量ベース)の大台を割り込んだ。異常事態である。酪農生産構造の危機的なシグナルと受け止めたい。特に都府県の基盤弱体化に歯止めがかからず、夏場の飲用牛乳ひっ迫の懸念が一段と高まってきた。政官民挙げて、緊急的な都府県酪農支援対策が必要だ。
酪農・乳業界は現在、三つのリスクに直面している。貿易自由化の加速化に伴う輸入乳製品の攻勢、生産基盤弱体化の進展、規制緩和の圧力を通じた競争促進の側面が強まった酪農政策への転換だ。自由化、生産基盤、農政の3リスクが、酪農・乳業の足元を大きく揺さぶる。
こうした中で、中央酪農会議(中酪)がまとめた指定生乳生産者団体(指定団体)の17年度総受託乳量(沖縄県を除く)は約698万トンとなった。700万トン割れは1987年以来。大台割れは、弱体化が進む酪農生産構造の象徴的な意味を持つと言っていい。問題は、増産に転じた北海道と、減産幅が大きくなっている都府県の地域別格差が広がっていることだ。
酪農・乳業界は現在、三つのリスクに直面している。貿易自由化の加速化に伴う輸入乳製品の攻勢、生産基盤弱体化の進展、規制緩和の圧力を通じた競争促進の側面が強まった酪農政策への転換だ。自由化、生産基盤、農政の3リスクが、酪農・乳業の足元を大きく揺さぶる。
こうした中で、中央酪農会議(中酪)がまとめた指定生乳生産者団体(指定団体)の17年度総受託乳量(沖縄県を除く)は約698万トンとなった。700万トン割れは1987年以来。大台割れは、弱体化が進む酪農生産構造の象徴的な意味を持つと言っていい。問題は、増産に転じた北海道と、減産幅が大きくなっている都府県の地域別格差が広がっていることだ。
持続的で多様な酪農共存を
乳業メーカーや農業団体などで構成するJミルクは、今年度からの中期事業指針の新3カ年計画を決めた。最大の柱は酪農生産基盤の維持、強化だ。多様な経営体が共存する持続可能な日本型酪農を目指す。酪農・乳業界は現在、半世紀ぶりの大転換期を迎えている。ミルクの価値向上と共に、関係者一丸の生産基盤支援が急務の課題だ。
Jミルクは生産・処理・販売を担う関係者で、国民に安定的に牛乳・乳製品を供給するミルク・サプライチェーンの確立を進める。だが現在、大きな岐路に立たされていると言っていい。国内生乳生産の減少に歯止めがかからないことだ。西尾啓治会長(雪印メグミルク社長)は「業界の発展には国産原料乳の安定確保が大前提だ。特に深刻な都府県酪農の地盤沈下をどうするのかが大きな課題となる」と、今年度からの3カ年計画の重点を強調する。
こうした危機意識は業界全体に共通している。かつて、飲用乳価交渉で酪農団体と乳業メーカーが激しく対立した構図が一変。互いに運命共同体の「酪農・乳業一体論」が広がる。両者で、巨大の販売力で低価格を押し付ける大手スーパー対策や輸入乳製品への対応などで手を結ぶ。
業界の声を代弁し今後、Jミルクが力を入れるのが価格競争から価値競争への転換だ。飲用牛乳のスーパーでの安売り合戦に見られる価格競争から、ミルクの持つ健康寿命を後押しする機能性などを前面に出した商品開発などの価値競争へ舵を切り、業界全体が付加価値産業のミルク・バリューチェーンへの脱皮を目指す。
ただ現状は、原料乳安定供給に暗雲が広がっているのが実態だ。2017年度の生乳生産実績に端的に表れた。受託乳量ベースで北海道が約380万トンと生産を維持する半面、都府県の減産が止まらない。業界では今後数年間で都府県の生産は300万トン割れとなるとの悲観的な見方も出ている。
北海道と都府県の酪農が一定のバランスを取りながら共存しなければ、生乳の用途別需給体制は大きな支障が出かねない。4月から施行した改正畜産経営安定法は、生乳流通の自由化を促す半面、乳価の高い飲用シフトを招きかねない。大型酪農家による指定団体とそれ以外の業者への「二股出荷」も顕在化してきた。農水省は別途、都府県の増頭を後押しする即効性のある緊急対策を打ち出し、用途別需給安定を図る必要がある。
Jミルクは今後、検討委員会で日本型酪農の在り方を具体化していく。ポイントは国内生産基盤の弱体化に歯止めをかけ、いかに持続可能な酪農生産体制を構築するのか。基本視座は家族経営や企業的経営などの「多様性」の確保だ。現在、年間出荷乳量1000トン以上のメガ酪農や1万トン以上のギガ酪農が増産を担う傾向が強まっている。だが、地域と共に生きる家族農業や複合経営も欠かせない。飼料用米振興を念頭に、地域全体で酪農と米を活用した水田酪農も日本型酪農として位置付けたい。
(次回「透視眼」は8月号)
Jミルクは生産・処理・販売を担う関係者で、国民に安定的に牛乳・乳製品を供給するミルク・サプライチェーンの確立を進める。だが現在、大きな岐路に立たされていると言っていい。国内生乳生産の減少に歯止めがかからないことだ。西尾啓治会長(雪印メグミルク社長)は「業界の発展には国産原料乳の安定確保が大前提だ。特に深刻な都府県酪農の地盤沈下をどうするのかが大きな課題となる」と、今年度からの3カ年計画の重点を強調する。
こうした危機意識は業界全体に共通している。かつて、飲用乳価交渉で酪農団体と乳業メーカーが激しく対立した構図が一変。互いに運命共同体の「酪農・乳業一体論」が広がる。両者で、巨大の販売力で低価格を押し付ける大手スーパー対策や輸入乳製品への対応などで手を結ぶ。
業界の声を代弁し今後、Jミルクが力を入れるのが価格競争から価値競争への転換だ。飲用牛乳のスーパーでの安売り合戦に見られる価格競争から、ミルクの持つ健康寿命を後押しする機能性などを前面に出した商品開発などの価値競争へ舵を切り、業界全体が付加価値産業のミルク・バリューチェーンへの脱皮を目指す。
ただ現状は、原料乳安定供給に暗雲が広がっているのが実態だ。2017年度の生乳生産実績に端的に表れた。受託乳量ベースで北海道が約380万トンと生産を維持する半面、都府県の減産が止まらない。業界では今後数年間で都府県の生産は300万トン割れとなるとの悲観的な見方も出ている。
北海道と都府県の酪農が一定のバランスを取りながら共存しなければ、生乳の用途別需給体制は大きな支障が出かねない。4月から施行した改正畜産経営安定法は、生乳流通の自由化を促す半面、乳価の高い飲用シフトを招きかねない。大型酪農家による指定団体とそれ以外の業者への「二股出荷」も顕在化してきた。農水省は別途、都府県の増頭を後押しする即効性のある緊急対策を打ち出し、用途別需給安定を図る必要がある。
Jミルクは今後、検討委員会で日本型酪農の在り方を具体化していく。ポイントは国内生産基盤の弱体化に歯止めをかけ、いかに持続可能な酪農生産体制を構築するのか。基本視座は家族経営や企業的経営などの「多様性」の確保だ。現在、年間出荷乳量1000トン以上のメガ酪農や1万トン以上のギガ酪農が増産を担う傾向が強まっている。だが、地域と共に生きる家族農業や複合経営も欠かせない。飼料用米振興を念頭に、地域全体で酪農と米を活用した水田酪農も日本型酪農として位置付けたい。
(次回「透視眼」は8月号)
- 2026年 2月号
- 2026年 1月号
- 2025年 12月号
- 2025年 10月号
- 2025年 8月号
- 2025年 6月号
- 2025年 4月号
- 2025年 2月号
- 2025年 1月号
- 2024年 10月号
- 2024年 9月号
- 2024年 8月号
- 2024年 6月号
- 2024年 4月号
- 2024年 2月号
- 2024年 1月号
- 2023年 12月号
- 2023年 10月号
- 2023年 8月号
- 2023年 6月号
- 2023年 4月号
- 2023年 2月号
- 2023年 1月号
- 2022年 12月号
- 2022年 10月号
- 2022年 8月号
- 2022年 6月号
- 2022年 4月号
- 2022年 2月号
- 2022年 1月号
- 2021年 12月号
- 2021年 10月号
- 2021年 8月号
- 2021年 6月号
- 2021年 4月号
- 2021年 2月号
- 2021年 1月号
- 2020年 12月号
- 2020年 10月号
- 2020年 8月号
- 2020年 6月号
- 2020年 4月号
- 2020年 2月号
- 2020年 1月号
- 2019年 12月号
- 2019年 10月号
- 2019年 8月号
- 2019年 6月号
- 2019年 4月号
- 2019年 2月号
- 2019年 1月号
- 2018年 12月号
- 2018年 10月号
- 2018年 8月号
- 2018年 6月号
- 2018年 4月号
- 2018年 2月号
- 2018年 1月号
- 2017年 12月号
- 2017年 10月号
- 2017年 8月号
- 2017年 6月号
- 2017年 4月号
- 2017年 2月号
- 2017年 1月号
- 2016年 12月号
- 2016年 10月号
- 2016年 8月号
- 2016年 6月号
- 2016年 4月号
- 2016年 2月号
- 2016年 1月号


