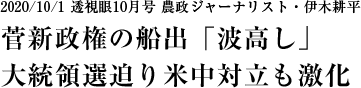
しかし、政治は生き物、「一寸先は闇」とはよく言ったものだ。本欄10月号でまさかの菅新政権の話を書こうとは。だがこの政権の行く手は「波高し」と言わざるを得ない。全ては1カ月後の米大統領選の結果次第だ。トランプ、バイデンどちらがなるにしても米中対立は続く。一層の乳製品自由化をはじめ新たな通商問題も浮上しかねない。課題山積の農政の中で官房副長官も務めた野上浩太郎新農相の手腕に警戒も含め注視したい。
新政権と規制改革への懸念
菅新政権で野上新農相は農産物の輸出拡大、生産基盤の拡充と食料自給率向上による食料安全保障を強調した。問題は規制改革の推進の行方だ。菅氏は官房長官時代に農協改革、全農改革、指定生乳生産者団体の弱体化につながる酪農制度改革の陣頭指揮を執った。当時、農水省は奥原正明という改革派事務次官が菅氏の指示で辣腕をふるった。結果、生産現場無視の「改悪」がまかり通った。酪農制度改革も、その後の生乳需給ひっ迫や新型コロナ禍対応などを見てもかえって指定団体機能の必要性こそ改めて認識されている。指定団体は弱体化ではなく逆に機能強化が必要だったことが裏付けされた。
さて今後の菅政権は規制改革路線を再び敷いてくる可能性がある。十分な監視と警戒が必要だ。衆院議員の任期まで1年余る。政局が揺れ動く。いつ解散・総選挙になってもおかしくない。要は生産現場の声を政治家に届け、「改悪」ではなく「改正」、正しい「規制緩和」を実施することだ。酪農家の声を一つにした酪農政治パワーの発揮の時でもあろう。
さて今後の菅政権は規制改革路線を再び敷いてくる可能性がある。十分な監視と警戒が必要だ。衆院議員の任期まで1年余る。政局が揺れ動く。いつ解散・総選挙になってもおかしくない。要は生産現場の声を政治家に届け、「改悪」ではなく「改正」、正しい「規制緩和」を実施することだ。酪農家の声を一つにした酪農政治パワーの発揮の時でもあろう。
「酪農版ブラックアウト」の教訓
今年もとんでもないスーパー台風、猛暑など異常気象、災害が相次ぐ。こうした中で2年前の2018年9月6日午前3時過ぎの震度7を記録した北海道地震を想起したい。前代未聞の全道停電は日本一の酪農産地を窮地に追いやった。電源がなく搾乳できない、絞った生乳を冷却できない。乳製品工場も稼働せず廃棄を余儀なくされた。水道は止まり牛に水もやれない。こんな「酪農版ブラックアウト」の中で多くの教訓を得た。
大規模停電は農業にも被害を及ぼした。特に年間で全国の6割弱の生乳生産400万トンを誇る酪農が大きな問題となった。搾った生乳を冷却しないと2時間ほどで乳質が劣化し販売できなくなる。販売できなくても搾り続けないと牛は乳房炎を発生する。しかも、冷却した生乳を乳業に持ち込んでも、乳製品工場が稼働できず廃棄したケースも出た。停電に伴う生乳廃棄は「酪農版ブラックアウト」と称され、行政、農業団体をはじめ関係機関挙げて広域配乳調整など対応が取られた。
2年前の「酪農版ブラックアウト」の緊急事態を踏まえ、農水省や道も支援を実施した。大きな柱が、酪農家ごとに自家発電設備(配電盤)の導入助成だ。道の調査では8月末現在で道内5200戸酪農家のうち3800戸(73パーセント)で導入したことが分かった。1年前の40パーセントから拡大した。今年度中に約8割に広がる見通しという。特に道東の大規模酪農地帯で顕著だ。
自家発電機や電源を切り替える配電盤設置費用の補助、酪農産地のJAによる独自支援策が後押しした成果だ。主産地JAでは組合員に貸し出す自家発電機の所有も拡充してきた。生乳を受け入れる乳業メーカーの自家発電設備導入も進む。よつ葉乳業は道内2工場から全4工場に拡大した。
こうした中で、北海道の農業団体は今年から毎年9月6日を「防災の日」とし、9月1日から6日までを「防災期間」に設定した。全道停電による2年前の惨事を教訓にし、災害への供えを改めて認識するためだ。台風が相次ぐ秋と重なる道独自の「防災期間」を、災害の供えの再確認の時期としたい。都府県酪農も他人ごとではない。広域停電を伴う大災害はいつどこでもあり得る。
大規模停電は農業にも被害を及ぼした。特に年間で全国の6割弱の生乳生産400万トンを誇る酪農が大きな問題となった。搾った生乳を冷却しないと2時間ほどで乳質が劣化し販売できなくなる。販売できなくても搾り続けないと牛は乳房炎を発生する。しかも、冷却した生乳を乳業に持ち込んでも、乳製品工場が稼働できず廃棄したケースも出た。停電に伴う生乳廃棄は「酪農版ブラックアウト」と称され、行政、農業団体をはじめ関係機関挙げて広域配乳調整など対応が取られた。
2年前の「酪農版ブラックアウト」の緊急事態を踏まえ、農水省や道も支援を実施した。大きな柱が、酪農家ごとに自家発電設備(配電盤)の導入助成だ。道の調査では8月末現在で道内5200戸酪農家のうち3800戸(73パーセント)で導入したことが分かった。1年前の40パーセントから拡大した。今年度中に約8割に広がる見通しという。特に道東の大規模酪農地帯で顕著だ。
自家発電機や電源を切り替える配電盤設置費用の補助、酪農産地のJAによる独自支援策が後押しした成果だ。主産地JAでは組合員に貸し出す自家発電機の所有も拡充してきた。生乳を受け入れる乳業メーカーの自家発電設備導入も進む。よつ葉乳業は道内2工場から全4工場に拡大した。
こうした中で、北海道の農業団体は今年から毎年9月6日を「防災の日」とし、9月1日から6日までを「防災期間」に設定した。全道停電による2年前の惨事を教訓にし、災害への供えを改めて認識するためだ。台風が相次ぐ秋と重なる道独自の「防災期間」を、災害の供えの再確認の時期としたい。都府県酪農も他人ごとではない。広域停電を伴う大災害はいつどこでもあり得る。
米大統領選まで1カ月
11月3日投開票の米大統領選まであと1カ月余り。結果詳細は次回12月号「透視眼」で紹介したい。現職のトランプ大統領(共和党)とバイデン前副大統領(民主党)が激突し、直前まで接戦となる見通しだ。両者は対中国強硬姿勢で一致する一方で、対外政策では見解が異なる。通商問題は、バイデン氏も自国労働者保護を掲げ今後の論争で注視が必要だ。
選挙戦の構図は、大まかに言えばトランプ氏の「米国第一主義」対バイデン氏の同盟国なども重視した「国際協調主義」の選択である。まだ抽象的な表現が多く今後の両者の論争を通じた具体的な言及に注目したい。特に、対中政策や日本の農業にとっても大きな影響がある環太平洋連携協定(TPP)など今後の通商対応で、どういった議論が交わさされるかも焦点だ。
収束のめどが立たない新型コロナウイルス禍の対応も焦点だ。米国の感染者は約600万人と世界で最も多い。トランプ氏は、現職の強みを最大限に発揮し好景気のまま一気に大統領選に突入し再選を目指すシナリオだったが、新型コロナ禍で選挙戦略は大幅に狂い劣勢に立たされている。逆にバイデン氏は現政権の対応のまずさを追及する。だが、感染を抑制する新ワクチン開発にめどが立てば情勢は一転しかねない。
トランプ氏の独自路線は、国際機関との協調を軽視し、欧州をはじめ同盟国とのあつれきが生じ、中東情勢もかえって悪化を招いた。米国内でも分断と対立が強まり、メディアからも批判が繰り返されてきた。こうした中で、選挙情勢はバイデン氏有利が続く。最近の世論調査でもバイデン氏がトランプ氏を支持率で上回る。それでも、1カ月後の投開票直前まで接戦を予測する見方が多いのは、4年前のトランプ氏の大逆転勝利を踏まえてのことだ。
大統領選は、全米50州と首都ワシントンに割り当てられた選挙人計538人のうち過半数(270人)を獲得した候補者は当選する。基本的には各州の選挙人は勝者が総取りするため、州別の勝敗が鍵を握る。激戦州は十数州あり、中でも大票田の南部のテキサス州、南東部フロリダ州の行方は、大統領選の勝敗に直結する。
総取り方式は共和党に有利に働くともされる。事前調査で有利とされた前回の民主党候補ヒラリー・クリントン氏は総得票数でトランプ氏を約300万票上回ったが、複数の接戦州を僅差で落とし結果的に敗北した。困窮した白人労働者の支持を得られなかったことが大きい。
指名受諾演説でバイデン氏は、公民権運動の巨星・エラ・ベイカーの言葉から語り始め、協調と共感を訴えた。経済再建や気候変動に触れたがTPPをはじめ通商政策にはほとんど言及しなかった。対するトランプ氏はしたたかだ。バイデン氏を「副大統領時代にTPPを支持し中国の台頭を許した」と指摘。「社会主義のトロイの木馬」だと攻撃した。今後、直接対決になるテレビ討論などを経て、支持率が変化する可能性もある。
農民票の動向にも注目だ。元々、農業者は共和党支持者が多いが、貿易戦争の激化に不満が募る。トランプ政権は、補助金を手厚くするなど農民票のつなぎとめに賢明に動く。輸出産業である米国農業で両者の言及にも注視が必要だ。
選挙戦の構図は、大まかに言えばトランプ氏の「米国第一主義」対バイデン氏の同盟国なども重視した「国際協調主義」の選択である。まだ抽象的な表現が多く今後の両者の論争を通じた具体的な言及に注目したい。特に、対中政策や日本の農業にとっても大きな影響がある環太平洋連携協定(TPP)など今後の通商対応で、どういった議論が交わさされるかも焦点だ。
収束のめどが立たない新型コロナウイルス禍の対応も焦点だ。米国の感染者は約600万人と世界で最も多い。トランプ氏は、現職の強みを最大限に発揮し好景気のまま一気に大統領選に突入し再選を目指すシナリオだったが、新型コロナ禍で選挙戦略は大幅に狂い劣勢に立たされている。逆にバイデン氏は現政権の対応のまずさを追及する。だが、感染を抑制する新ワクチン開発にめどが立てば情勢は一転しかねない。
トランプ氏の独自路線は、国際機関との協調を軽視し、欧州をはじめ同盟国とのあつれきが生じ、中東情勢もかえって悪化を招いた。米国内でも分断と対立が強まり、メディアからも批判が繰り返されてきた。こうした中で、選挙情勢はバイデン氏有利が続く。最近の世論調査でもバイデン氏がトランプ氏を支持率で上回る。それでも、1カ月後の投開票直前まで接戦を予測する見方が多いのは、4年前のトランプ氏の大逆転勝利を踏まえてのことだ。
大統領選は、全米50州と首都ワシントンに割り当てられた選挙人計538人のうち過半数(270人)を獲得した候補者は当選する。基本的には各州の選挙人は勝者が総取りするため、州別の勝敗が鍵を握る。激戦州は十数州あり、中でも大票田の南部のテキサス州、南東部フロリダ州の行方は、大統領選の勝敗に直結する。
総取り方式は共和党に有利に働くともされる。事前調査で有利とされた前回の民主党候補ヒラリー・クリントン氏は総得票数でトランプ氏を約300万票上回ったが、複数の接戦州を僅差で落とし結果的に敗北した。困窮した白人労働者の支持を得られなかったことが大きい。
指名受諾演説でバイデン氏は、公民権運動の巨星・エラ・ベイカーの言葉から語り始め、協調と共感を訴えた。経済再建や気候変動に触れたがTPPをはじめ通商政策にはほとんど言及しなかった。対するトランプ氏はしたたかだ。バイデン氏を「副大統領時代にTPPを支持し中国の台頭を許した」と指摘。「社会主義のトロイの木馬」だと攻撃した。今後、直接対決になるテレビ討論などを経て、支持率が変化する可能性もある。
農民票の動向にも注目だ。元々、農業者は共和党支持者が多いが、貿易戦争の激化に不満が募る。トランプ政権は、補助金を手厚くするなど農民票のつなぎとめに賢明に動く。輸出産業である米国農業で両者の言及にも注視が必要だ。
人口減50万人超で需要どうなる
日本人の総人口の減少幅が初めて年間50万人を超えた。〈50万ショック〉は、少子高齢化の加速を裏付け国内産業に大きな変革を迫る。人口減は需要減となり食料需給にも深刻な影響を及ぼす。国は、米をはじめ国内農畜産物の需要拡大も含め、今後の政策見直しを急ぐべきだ。
人口減が止まらず、しかも速度を増している。人口は人の口と書く。口が減れば胃袋の数も少なくなり、食の国内消費に大きな影響を及ぼす。一方で、食料自給率が38パーセント(カロリー換算)という実態は、人口減少を踏まえながらも輸入品を国産に切り替える余地が大きい実態も示す。
総務省は、住民基本台帳に基づく今年1月1日現在の日本の人口を1億2427万1318人になったと発表した。前年に比べ50万5046人(0・4パーセント)減少した。人口は2009年をピークに11年連続で減り、減少幅は1968年の調査開始以降、最大となった。
減少幅は初めて50万人を超えた。1年間で鳥取県の人口(約55万6000人)に近い人口が減ったことになる。50万人減という数字を衝撃を持って受け止めねばならない。日本人の出生者は約86万6千人と1979年度以降で最少、逆に死亡者数は約137万8千人で最多だった。少子化社会は多死社会と裏表である。一方で、日本に住む外国人は前年より7・48パーセント増え約286万6千人となり6年連続で増えた。地域別には東京など3都県が増え、首都圏の一極集中が続く。半面で、地方への田園回帰と関係人口の増加に伴う「にぎやかな過疎」の動きにも注目したい。こうした日本の人口構図を踏まえ、今後の対応を急がねばならない。
少子高齢化を巡って、日本には既にいつくかのショックが襲ってきた。平成元年の1989年には、1人の女性が一生に産む子どもの平均数を示す合計特殊出生率が過去最低の1・57となった。直近の19年の出生率は1・36と低下に歯止めたかからない。出生数は国の当初予想より早く90万人の大台を割り込み「86万ショック」との言葉もうまれた。平成の30年は「少子化を傍観した時代」とさえ指摘される。
こうした中で、流通大手のセブン&アイ・ホールディングスは8月、米国コンビニ3位の企業を約2兆2千億円で買収したと発表した。今回の巨額買収の背景には、国内市場で今後大きな成長が見込めないとの判断があった。加速する人口減が、流通業界や食品業界の企業戦略に影響を与えている表れだ。
人口減、少子高齢化は農畜産物の需要も左右する。特に、ほぼ全量自給している主食用米への消費減は深刻だ。農水省は、人口減を踏まえ年間の需要減は10万トンと見込む。これに、新型コロナウイルス禍による外食など業務用需要減少が長期化する恐れがある。需給調整に影響が及ぶのは必至だ。畜産と連携した転作拡大と併せ、効果的で実需に結び付く新たな消費拡大策が欠かせない。
簡便化、健康・国産志向など食の現場の構造変化は、おにぎりや弁当など米の中食需要を増やし、スーパーでの野菜サラダなど総菜需要を押し上げている。農業団体では、総菜の国産食材への切り替えを進めコンビニでの販売拡大を目指す。秋田県大潟村では、中食需要をにらみ来春稼働へ県内初のパックご飯工場計画も進む。酪農乳業は業界挙げ健康志向で好調な生乳需要に応じるため、生産地盤沈下の著しい都府県酪農の増産支援を強めている。高齢化は少量の食べ切りサイズの提供も促す。農産物直売所での対応も必要だろう。
今回の〈50万人減ショック〉と自給率引き上げを両にらみした政策実施を急ぐべきだ。国は、関係団体と連携し国内農業振興と主食用米から他作物への転換後押しに一層力を入れねばならない。
牛乳・乳製品は米とは大きく異なる。今後10年を見据えた新たな基本計画、酪肉近でも需要を780万トンと現行水準の50万トンを明記し国内酪農の増産を促す。ただ一方で人口減少の影響は深刻に考えざるを得ない。特に少子高齢化は牛乳・乳製品の今後の需要に暗い影を落とすことは間違いない。人口減は労働力不足にも結び付く。省力化、スマート酪農促進の課題とも重なる。
(次回「透視眼」は12月号)
人口減が止まらず、しかも速度を増している。人口は人の口と書く。口が減れば胃袋の数も少なくなり、食の国内消費に大きな影響を及ぼす。一方で、食料自給率が38パーセント(カロリー換算)という実態は、人口減少を踏まえながらも輸入品を国産に切り替える余地が大きい実態も示す。
総務省は、住民基本台帳に基づく今年1月1日現在の日本の人口を1億2427万1318人になったと発表した。前年に比べ50万5046人(0・4パーセント)減少した。人口は2009年をピークに11年連続で減り、減少幅は1968年の調査開始以降、最大となった。
減少幅は初めて50万人を超えた。1年間で鳥取県の人口(約55万6000人)に近い人口が減ったことになる。50万人減という数字を衝撃を持って受け止めねばならない。日本人の出生者は約86万6千人と1979年度以降で最少、逆に死亡者数は約137万8千人で最多だった。少子化社会は多死社会と裏表である。一方で、日本に住む外国人は前年より7・48パーセント増え約286万6千人となり6年連続で増えた。地域別には東京など3都県が増え、首都圏の一極集中が続く。半面で、地方への田園回帰と関係人口の増加に伴う「にぎやかな過疎」の動きにも注目したい。こうした日本の人口構図を踏まえ、今後の対応を急がねばならない。
少子高齢化を巡って、日本には既にいつくかのショックが襲ってきた。平成元年の1989年には、1人の女性が一生に産む子どもの平均数を示す合計特殊出生率が過去最低の1・57となった。直近の19年の出生率は1・36と低下に歯止めたかからない。出生数は国の当初予想より早く90万人の大台を割り込み「86万ショック」との言葉もうまれた。平成の30年は「少子化を傍観した時代」とさえ指摘される。
こうした中で、流通大手のセブン&アイ・ホールディングスは8月、米国コンビニ3位の企業を約2兆2千億円で買収したと発表した。今回の巨額買収の背景には、国内市場で今後大きな成長が見込めないとの判断があった。加速する人口減が、流通業界や食品業界の企業戦略に影響を与えている表れだ。
人口減、少子高齢化は農畜産物の需要も左右する。特に、ほぼ全量自給している主食用米への消費減は深刻だ。農水省は、人口減を踏まえ年間の需要減は10万トンと見込む。これに、新型コロナウイルス禍による外食など業務用需要減少が長期化する恐れがある。需給調整に影響が及ぶのは必至だ。畜産と連携した転作拡大と併せ、効果的で実需に結び付く新たな消費拡大策が欠かせない。
簡便化、健康・国産志向など食の現場の構造変化は、おにぎりや弁当など米の中食需要を増やし、スーパーでの野菜サラダなど総菜需要を押し上げている。農業団体では、総菜の国産食材への切り替えを進めコンビニでの販売拡大を目指す。秋田県大潟村では、中食需要をにらみ来春稼働へ県内初のパックご飯工場計画も進む。酪農乳業は業界挙げ健康志向で好調な生乳需要に応じるため、生産地盤沈下の著しい都府県酪農の増産支援を強めている。高齢化は少量の食べ切りサイズの提供も促す。農産物直売所での対応も必要だろう。
今回の〈50万人減ショック〉と自給率引き上げを両にらみした政策実施を急ぐべきだ。国は、関係団体と連携し国内農業振興と主食用米から他作物への転換後押しに一層力を入れねばならない。
牛乳・乳製品は米とは大きく異なる。今後10年を見据えた新たな基本計画、酪肉近でも需要を780万トンと現行水準の50万トンを明記し国内酪農の増産を促す。ただ一方で人口減少の影響は深刻に考えざるを得ない。特に少子高齢化は牛乳・乳製品の今後の需要に暗い影を落とすことは間違いない。人口減は労働力不足にも結び付く。省力化、スマート酪農促進の課題とも重なる。
(次回「透視眼」は12月号)
- 2024年 10月号
- 2024年 9月号
- 2024年 8月号
- 2024年 6月号
- 2024年 4月号
- 2024年 2月号
- 2024年 1月号
- 2023年 12月号
- 2023年 10月号
- 2023年 8月号
- 2023年 6月号
- 2023年 4月号
- 2023年 2月号
- 2023年 1月号
- 2022年 12月号
- 2022年 10月号
- 2022年 8月号
- 2022年 6月号
- 2022年 4月号
- 2022年 2月号
- 2022年 1月号
- 2021年 12月号
- 2021年 10月号
- 2021年 8月号
- 2021年 6月号
- 2021年 4月号
- 2021年 2月号
- 2021年 1月号
- 2020年 12月号
- 2020年 10月号
- 2020年 8月号
- 2020年 6月号
- 2020年 4月号
- 2020年 2月号
- 2020年 1月号
- 2019年 12月号
- 2019年 10月号
- 2019年 8月号
- 2019年 6月号
- 2019年 4月号
- 2019年 2月号
- 2019年 1月号
- 2018年 12月号
- 2018年 10月号
- 2018年 8月号
- 2018年 6月号
- 2018年 4月号
- 2018年 2月号
- 2018年 1月号
- 2017年 12月号
- 2017年 10月号
- 2017年 8月号
- 2017年 6月号
- 2017年 4月号
- 2017年 2月号
- 2017年 1月号
- 2016年 12月号
- 2016年 10月号
- 2016年 8月号
- 2016年 6月号
- 2016年 4月号
- 2016年 2月号
- 2016年 1月号


