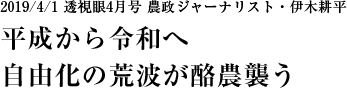
5月の改元、新天皇誕生が間近かに迫るの中で、平成の世があと1カ月足らずで終わる。平成の30年間を振り返れば、酪農、畜産には試練の時代が続いた。典型は相次ぐ貿易自由化だ。新元号の令和と共に、新たな展望を持ち、国際化が加速する日本酪農、家族農業を維持・発展させていかねばならない。
綱渡りの生乳需給続く
まずは、生乳全体の需給見通し。今年度の生乳需給も綱渡りが続く。Jミルクの需給予測は、前年度比0・9パーセント増と4年ぶりの増産見通しを示した。だが、都府県の生産基盤弱体化に一向に歯止めがかかっていない。4年ぶりの飲用乳価引き上げもてこに、官民挙げた着実な増産対策を進めるべきだ。
相次ぐ自由化で、酪農家の生産意欲に悪影響を及ぼさないか懸念する。年末の環太平洋連携協定(TPP)に続き、2月からは欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)が発効した。今春には日米新貿易協議も待つ。自由化の進展に伴う国産乳製品への打撃は、徐々に出てくると見込まれるが、生乳需給への影響に注視したい。
こうした中で、Jミルクの生乳需給見通しは、微増となった。北海道が昨秋の地震の影響から立ち直る見込みが大きい。半面で、都府県は減少幅は縮まってきたとはいえ減産傾向が続く。この需給見通しとセットで農水省は、来年度のバターと脱脂粉乳の輸入枠数量を発表した。注視したいのはバター2万トン(製品換算)と、1年前の当初枠に比べ7000トンと大幅に増やした点だ。需要が増えているためだが、今後とも需要増が続くかは不透明だ。
生乳換算にすれば約24万7000トンと酪農産地数県分の数量だ。それだけ、国内乳製品市況に影響を及ぼし、需給状況によっては来年度の乳製品価格交渉とも関連する。今年度は都府県対策を重視した大手乳業メーカーが指定生乳生産者団体との価格交渉で飲用向けを4年ぶりに引き上げで決着した。1キロ4円上げは、飲用向け約400トンで百億円台となる計算だ。一方で、加工向けは乳業によって対応は分かれたが、ホクレンとの交渉で最終的に据え置きで決着した。
酪農家サイドで見れば、生乳用途別の割合で異なるが、増産による所得増加効果が大きい。だが、相次ぐ自由化で乳製品輸入は拡大していく。さらに、今回のバター輸入枠の大幅拡大だ。記者会見で「バター輸入枠が大き過ぎないか」との指摘に同省は「あくまで枠であり5、9月の時点で国内生産状況を見て見直しもあり得る」とした。問題は夏場の天気と生乳生産の状況だ。改元絡みで4月末からの10連休で学校給食向け牛乳の休止もある。夏場の気温は低ければ、一挙に加工向けが増える可能性もある。政府は国内の用途別需給を精査し、輸入枠変更に迅速に対応すべきだ。
需給見通しを全体的にみると、やはり9月の需給が例年以上に綱渡りとなるのは間違いない。9月の道外生乳移出量は前年同期比23パーセント増の6万トン強と、輸送能力の限界に近い数量を見込む。昨秋の北海道地震の教訓は北海道と都府県の均衡ある酪農発展だったはずだ。都府県の底上げが欠かせない。
気になるのが、輸入枠発表時に示した同省の今後の国内生乳生産のあまりに楽観的な見通しだ。2歳未満の未経産牛の増頭などから、6年後の長期目標である750万トンに向け「順調に回復していく」とした。自由化が加速し、生産コストが上がる中で果たしてそうか。国は畜産クラスターや初任牛導入対策など対応しているが、今後は償還返済や家畜ふん尿処理の環境対策などの課題もある。今後は中山間地や家族農業にも農政の光を当てながら、北海道と都府県の均衡発展をより強固に視座に据えた酪農行政こそ問われている。
相次ぐ自由化で、酪農家の生産意欲に悪影響を及ぼさないか懸念する。年末の環太平洋連携協定(TPP)に続き、2月からは欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)が発効した。今春には日米新貿易協議も待つ。自由化の進展に伴う国産乳製品への打撃は、徐々に出てくると見込まれるが、生乳需給への影響に注視したい。
こうした中で、Jミルクの生乳需給見通しは、微増となった。北海道が昨秋の地震の影響から立ち直る見込みが大きい。半面で、都府県は減少幅は縮まってきたとはいえ減産傾向が続く。この需給見通しとセットで農水省は、来年度のバターと脱脂粉乳の輸入枠数量を発表した。注視したいのはバター2万トン(製品換算)と、1年前の当初枠に比べ7000トンと大幅に増やした点だ。需要が増えているためだが、今後とも需要増が続くかは不透明だ。
生乳換算にすれば約24万7000トンと酪農産地数県分の数量だ。それだけ、国内乳製品市況に影響を及ぼし、需給状況によっては来年度の乳製品価格交渉とも関連する。今年度は都府県対策を重視した大手乳業メーカーが指定生乳生産者団体との価格交渉で飲用向けを4年ぶりに引き上げで決着した。1キロ4円上げは、飲用向け約400トンで百億円台となる計算だ。一方で、加工向けは乳業によって対応は分かれたが、ホクレンとの交渉で最終的に据え置きで決着した。
酪農家サイドで見れば、生乳用途別の割合で異なるが、増産による所得増加効果が大きい。だが、相次ぐ自由化で乳製品輸入は拡大していく。さらに、今回のバター輸入枠の大幅拡大だ。記者会見で「バター輸入枠が大き過ぎないか」との指摘に同省は「あくまで枠であり5、9月の時点で国内生産状況を見て見直しもあり得る」とした。問題は夏場の天気と生乳生産の状況だ。改元絡みで4月末からの10連休で学校給食向け牛乳の休止もある。夏場の気温は低ければ、一挙に加工向けが増える可能性もある。政府は国内の用途別需給を精査し、輸入枠変更に迅速に対応すべきだ。
需給見通しを全体的にみると、やはり9月の需給が例年以上に綱渡りとなるのは間違いない。9月の道外生乳移出量は前年同期比23パーセント増の6万トン強と、輸送能力の限界に近い数量を見込む。昨秋の北海道地震の教訓は北海道と都府県の均衡ある酪農発展だったはずだ。都府県の底上げが欠かせない。
気になるのが、輸入枠発表時に示した同省の今後の国内生乳生産のあまりに楽観的な見通しだ。2歳未満の未経産牛の増頭などから、6年後の長期目標である750万トンに向け「順調に回復していく」とした。自由化が加速し、生産コストが上がる中で果たしてそうか。国は畜産クラスターや初任牛導入対策など対応しているが、今後は償還返済や家畜ふん尿処理の環境対策などの課題もある。今後は中山間地や家族農業にも農政の光を当てながら、北海道と都府県の均衡発展をより強固に視座に据えた酪農行政こそ問われている。
米中対立が日本に波及
トランプ米政権誕生から2年余り。米中対立に典型的な貿易問題の行方は、今後の日米協議にも影響を及ぼすのは必至だ。
米国際政治学者のイアン・ブレマー氏が示した2019年の世界10大リスクの筆頭に挙げた「悪い種」は、今の状況を端的に表す。「悪い種」とは米欧政治の混迷や西側同盟関係の弱体化などで、その種が世界中にばらまかれ、芽を出し生長しかねない懸念を示したものだ。トランプ政権は今、任期4年の折り返し地点を回り、2020年、東京五輪後の来年11月の次期大統領選に照準を当てた、さまざまな「米国第一」カードを持ちトランプ流ディール(取引)を繰り広げる。
トランプ政権3年目に入り、当面の最大懸念は〝3月リスク〟と言われる事態だ。まずは「ハイテク新冷戦」とも称される米中貿易紛争の行方だ。トランプ、習金近中国国家主席が決めた米中の「90日協議」は3月1日が期限。不調に終われば貿易戦争は泥沼化するとの予測が強かったが、交渉は「一時休戦」となった。米国債のデフォルト(債務不履行)懸念も高まる。連邦政府の借金が法定限度額に達し、米議会が債務上限を上げないと数カ月で資金は枯渇する。昨年11月の中間選挙で、現在、下院は野党・民主党が多数を占める「ねじれ」状態だけに、先行きは不透明感を増す。安定している米国債の格下げも想定される事態は、国際金融システムに黄信号がともることを意味する。
この〝3月リスク〟を前に、トランプ氏が仕掛けたのが2月末とされる米朝首脳会談だ。両国で何らかの妥協が成立すれば、米国内の不満は外交に向く。
日本は、4月ともされる日米新貿易協議に身構える。まずは、米中協議がどういった結果となるかで米国の対日戦略も変化する。米中貿易戦争の激化で、中国経済は減速過程に入った。習主席主導の対外経済戦略「一帯一路」にも暗雲が漂う。3月上旬の国会に当たる全国人民代表会議(全人代)で、米中貿易紛争も念頭に、中国は経済成長目標を下方修正した。習主席は和戦両様で打開策を探る。ただ、あまりトランプ氏に譲歩過ぎれば、中国国内の反発を招き、自身の権力基盤を弱める恐れもある。一方で対米貿易黒字は膨らみ続け、思い切った市場開放と米国製品の買い入れも検討中とされる。
中国の対米譲歩の内容次第で、トランプ氏は対日圧力を強めかねない。日米協議で最大の焦点は自動車だが、トランプ政権閣僚は同時に農畜産物の対日輸出拡大も繰り返し明らかにしている。
安倍首相は、米国抜きの11カ国によるTPP発効をてこに、トランプ氏へ多国間協議復帰を目指す。だが、米国の2国間協議重視の姿勢は揺るがない。TPPの3文字の意味合いは、既に「トランプ・パートナーシップ・プロブレム」に変化している。つまり、いかにトランプ氏と友好関係を強まるかが最大の問題となっている。
先の「悪い種」を芽吹かせないためにも、日本はWTOによる国際協調路線を主導する必要がある。日米協議を前に、関税撤廃で国内農業に犠牲を強いる「TPP型市場開放路線」には将来展望がないことを、安倍政権は自覚すべきだ。
米国際政治学者のイアン・ブレマー氏が示した2019年の世界10大リスクの筆頭に挙げた「悪い種」は、今の状況を端的に表す。「悪い種」とは米欧政治の混迷や西側同盟関係の弱体化などで、その種が世界中にばらまかれ、芽を出し生長しかねない懸念を示したものだ。トランプ政権は今、任期4年の折り返し地点を回り、2020年、東京五輪後の来年11月の次期大統領選に照準を当てた、さまざまな「米国第一」カードを持ちトランプ流ディール(取引)を繰り広げる。
トランプ政権3年目に入り、当面の最大懸念は〝3月リスク〟と言われる事態だ。まずは「ハイテク新冷戦」とも称される米中貿易紛争の行方だ。トランプ、習金近中国国家主席が決めた米中の「90日協議」は3月1日が期限。不調に終われば貿易戦争は泥沼化するとの予測が強かったが、交渉は「一時休戦」となった。米国債のデフォルト(債務不履行)懸念も高まる。連邦政府の借金が法定限度額に達し、米議会が債務上限を上げないと数カ月で資金は枯渇する。昨年11月の中間選挙で、現在、下院は野党・民主党が多数を占める「ねじれ」状態だけに、先行きは不透明感を増す。安定している米国債の格下げも想定される事態は、国際金融システムに黄信号がともることを意味する。
この〝3月リスク〟を前に、トランプ氏が仕掛けたのが2月末とされる米朝首脳会談だ。両国で何らかの妥協が成立すれば、米国内の不満は外交に向く。
日本は、4月ともされる日米新貿易協議に身構える。まずは、米中協議がどういった結果となるかで米国の対日戦略も変化する。米中貿易戦争の激化で、中国経済は減速過程に入った。習主席主導の対外経済戦略「一帯一路」にも暗雲が漂う。3月上旬の国会に当たる全国人民代表会議(全人代)で、米中貿易紛争も念頭に、中国は経済成長目標を下方修正した。習主席は和戦両様で打開策を探る。ただ、あまりトランプ氏に譲歩過ぎれば、中国国内の反発を招き、自身の権力基盤を弱める恐れもある。一方で対米貿易黒字は膨らみ続け、思い切った市場開放と米国製品の買い入れも検討中とされる。
中国の対米譲歩の内容次第で、トランプ氏は対日圧力を強めかねない。日米協議で最大の焦点は自動車だが、トランプ政権閣僚は同時に農畜産物の対日輸出拡大も繰り返し明らかにしている。
安倍首相は、米国抜きの11カ国によるTPP発効をてこに、トランプ氏へ多国間協議復帰を目指す。だが、米国の2国間協議重視の姿勢は揺るがない。TPPの3文字の意味合いは、既に「トランプ・パートナーシップ・プロブレム」に変化している。つまり、いかにトランプ氏と友好関係を強まるかが最大の問題となっている。
先の「悪い種」を芽吹かせないためにも、日本はWTOによる国際協調路線を主導する必要がある。日米協議を前に、関税撤廃で国内農業に犠牲を強いる「TPP型市場開放路線」には将来展望がないことを、安倍政権は自覚すべきだ。
どう見る平成年農政史
平成の30年間は激動の歴史と重なる。農政面で見れば、空前の自由化規制緩和で政策の軌道修正を余儀なくされた。政府は国内対策を拡充するが、生産基盤弱体化が進み、今後の展望が見えない。国際的潮流は持続可能性が問われる。成長一辺倒の農政から転換し、地域、家族農業にも重点を置くべきだ。
安倍首相は年頭の会見で「日本が先頭に立ち保護主義とたたかう」と強調した。トランプ米大統領の言動や、6月に大阪で開く20カ国・地域によるG20首脳会議の議長としての役割と責任を念頭に置いたものだ。平成の30年間を締めくくる言葉でもあろう。首相は、保護主義の対語を自由貿易と読み替え、これまでにない市場開放を断行してきた。だが、それは食料主権を失い、国民の胃袋と生存権をますます外国に委ねることにもつながる。
福知山公立大の矢口芳生教授は平成30年間の農政キーワードを貿易自由化、規制緩和、大規模化の三つを挙げる。この3元連立方程式は、農業の競争力や効率化ばかりが強調され、中山間地や家族農業軽視の政策と重なる。
平成元年に当たる1989年は「特異年」というべき、あらゆる歴史の分岐点に立っていた。最大の出来事は、米ソ和解による東西冷戦の終結だ。だがそれは、唯一の超大国・米国の存在感が増したことを示す。
同年、農業分野の市場開放に焦点を当てたガット・ウルグアイラウンド(多角的貿易交渉)の農業交渉が本格化した。米国は500億ドルと史上空前の規模に膨らんでいた対日貿易赤字にいらだち、次々と理不尽な自由化要求を迫った。転機は前年の88年、米通商代表部(USTR)ヤイター代表と佐藤隆農相(当時)の交渉を経た牛肉・オレンジ自由化決定だ。
いま一つの転換期は、米部分開放を受け入れた93年末のガット農業交渉合意だ。翌94年に農水省は食管法を廃止し食糧法を制定した。米の流通自由化が始まり生産者米価は下落。やがて、現在の生産調整抜本見直しにつながっていく。
戦後農政の歩みは『自民党農政史』(吉田修著)に詳しい。同著では、官邸ににらみを利かす必要から貿易対応には「歴代、自民党農林族のエースを充てた」と明かす。確かに、加藤紘一、羽田孜など党重鎮となるそうそうたる顔ぶれが並ぶ。今は森山裕元農相がその任に当たる。だが、自由化に抵抗した自民党農林族をもってしても、市場開放の激流は防げなかった。
日本の農政は1961年の農業基本法を起点にする。その後、平成に入り1992年に担い手の育成・確保を前面に掲げた新農政、そして21世紀目前の99年には新農基法と称された食料・農業・農村基本法が制定された。
総自由化の危機の中で農業再生への新たな国民運動の展開も欠かせない。中心は、国産農畜産物の増産を大前提とした食料安全保障の確立だろう。
農政の最大課題は、農業者の高齢化を踏まえた担い手確保と米偏重からの脱皮。構造的には戦後の農地解放で固定された小規模経営から大規模化への転換が問われた。特に米改革が日本農業そのものの改革と同義とさえ言えた。そこで、戦時統制経済でできた食糧管理法(食管法)から食糧法に移行する。これと併せ度重なる農地法改正も行う、現在は農地管理中間機構への一元化で、農地流動化、担い手への農地集積も進めるが、大規模化は足踏み状態が続く。
先の牛肉・オレンジ自由化は、農基法で定めた選択的拡大品目の市場開放を意味する。平成に入り農業大国との初めてのEPAとなったオーストラリアとの交渉で、国内農業の最後の砦として「重要5品目」を定めた。だが、TPPで、この5品目も関税削減・撤廃、輸入枠設定など譲歩を余儀なくされた。昨年末のTPP11発効で、日本は農業の総自由化時代に突入したと言っていい。
(次回「透視眼」は6月号)
安倍首相は年頭の会見で「日本が先頭に立ち保護主義とたたかう」と強調した。トランプ米大統領の言動や、6月に大阪で開く20カ国・地域によるG20首脳会議の議長としての役割と責任を念頭に置いたものだ。平成の30年間を締めくくる言葉でもあろう。首相は、保護主義の対語を自由貿易と読み替え、これまでにない市場開放を断行してきた。だが、それは食料主権を失い、国民の胃袋と生存権をますます外国に委ねることにもつながる。
福知山公立大の矢口芳生教授は平成30年間の農政キーワードを貿易自由化、規制緩和、大規模化の三つを挙げる。この3元連立方程式は、農業の競争力や効率化ばかりが強調され、中山間地や家族農業軽視の政策と重なる。
平成元年に当たる1989年は「特異年」というべき、あらゆる歴史の分岐点に立っていた。最大の出来事は、米ソ和解による東西冷戦の終結だ。だがそれは、唯一の超大国・米国の存在感が増したことを示す。
同年、農業分野の市場開放に焦点を当てたガット・ウルグアイラウンド(多角的貿易交渉)の農業交渉が本格化した。米国は500億ドルと史上空前の規模に膨らんでいた対日貿易赤字にいらだち、次々と理不尽な自由化要求を迫った。転機は前年の88年、米通商代表部(USTR)ヤイター代表と佐藤隆農相(当時)の交渉を経た牛肉・オレンジ自由化決定だ。
いま一つの転換期は、米部分開放を受け入れた93年末のガット農業交渉合意だ。翌94年に農水省は食管法を廃止し食糧法を制定した。米の流通自由化が始まり生産者米価は下落。やがて、現在の生産調整抜本見直しにつながっていく。
戦後農政の歩みは『自民党農政史』(吉田修著)に詳しい。同著では、官邸ににらみを利かす必要から貿易対応には「歴代、自民党農林族のエースを充てた」と明かす。確かに、加藤紘一、羽田孜など党重鎮となるそうそうたる顔ぶれが並ぶ。今は森山裕元農相がその任に当たる。だが、自由化に抵抗した自民党農林族をもってしても、市場開放の激流は防げなかった。
日本の農政は1961年の農業基本法を起点にする。その後、平成に入り1992年に担い手の育成・確保を前面に掲げた新農政、そして21世紀目前の99年には新農基法と称された食料・農業・農村基本法が制定された。
総自由化の危機の中で農業再生への新たな国民運動の展開も欠かせない。中心は、国産農畜産物の増産を大前提とした食料安全保障の確立だろう。
農政の最大課題は、農業者の高齢化を踏まえた担い手確保と米偏重からの脱皮。構造的には戦後の農地解放で固定された小規模経営から大規模化への転換が問われた。特に米改革が日本農業そのものの改革と同義とさえ言えた。そこで、戦時統制経済でできた食糧管理法(食管法)から食糧法に移行する。これと併せ度重なる農地法改正も行う、現在は農地管理中間機構への一元化で、農地流動化、担い手への農地集積も進めるが、大規模化は足踏み状態が続く。
先の牛肉・オレンジ自由化は、農基法で定めた選択的拡大品目の市場開放を意味する。平成に入り農業大国との初めてのEPAとなったオーストラリアとの交渉で、国内農業の最後の砦として「重要5品目」を定めた。だが、TPPで、この5品目も関税削減・撤廃、輸入枠設定など譲歩を余儀なくされた。昨年末のTPP11発効で、日本は農業の総自由化時代に突入したと言っていい。
(次回「透視眼」は6月号)
- 2025年 12月号
- 2025年 10月号
- 2025年 8月号
- 2025年 6月号
- 2025年 4月号
- 2025年 2月号
- 2025年 1月号
- 2024年 10月号
- 2024年 9月号
- 2024年 8月号
- 2024年 6月号
- 2024年 4月号
- 2024年 2月号
- 2024年 1月号
- 2023年 12月号
- 2023年 10月号
- 2023年 8月号
- 2023年 6月号
- 2023年 4月号
- 2023年 2月号
- 2023年 1月号
- 2022年 12月号
- 2022年 10月号
- 2022年 8月号
- 2022年 6月号
- 2022年 4月号
- 2022年 2月号
- 2022年 1月号
- 2021年 12月号
- 2021年 10月号
- 2021年 8月号
- 2021年 6月号
- 2021年 4月号
- 2021年 2月号
- 2021年 1月号
- 2020年 12月号
- 2020年 10月号
- 2020年 8月号
- 2020年 6月号
- 2020年 4月号
- 2020年 2月号
- 2020年 1月号
- 2019年 12月号
- 2019年 10月号
- 2019年 8月号
- 2019年 6月号
- 2019年 4月号
- 2019年 2月号
- 2019年 1月号
- 2018年 12月号
- 2018年 10月号
- 2018年 8月号
- 2018年 6月号
- 2018年 4月号
- 2018年 2月号
- 2018年 1月号
- 2017年 12月号
- 2017年 10月号
- 2017年 8月号
- 2017年 6月号
- 2017年 4月号
- 2017年 2月号
- 2017年 1月号
- 2016年 12月号
- 2016年 10月号
- 2016年 8月号
- 2016年 6月号
- 2016年 4月号
- 2016年 2月号
- 2016年 1月号


