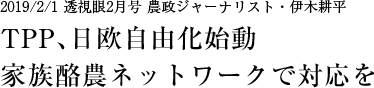
自由化の巨大波が日本農業を襲う。昨年末の環太平洋連携協定(TPP)11に続き、2月1日に欧州連合(EU)との通商協定が発効した。わが国は歴史上経験のない農業総自由化の新局面に入る。数年後には国内酪農への打撃も必至だ。これに抗するには、広範に存在する家族農業のネットワークで対応する以外にない。
4月には一段と関税削減
年末に発効したTPP11は、日本がこれまで約束したことのない市場開放を確約したものに他ならない。米、乳製品、牛肉など重要5品目に特段の配慮をしたものの、国内農業への打撃は避けられない。例えば、官民挙げて振興してきた国産チーズの先行きも不透明となった。農水省は、プロセス原料ナチュラルチーズの関税割当制度、国産と輸入物との現行抱き合わせの仕組みは維持したと主張するが、表面的な言い訳に過ぎない。有乳の関税が年々下がっていき、およそ4年後に抱き合わせ制度は効かなくなる。つまり、輸入品100パーセントでチーズ製造した方が有利になるのだ。抱き合わせ制度は形だけが残るに過ぎない。
米国抜きの11カ国によるTPP協定発効は、これまでの通商協議の地図を塗り替えかねない。前例のない農畜産物の自由化が進み、発効から約3カ月後の今年4月からは協定2年度目の一層の関税削減が迫られる。
最大で最も効果的な国内対策は、これ以上の自由化をしないことだ。TPP11発効は、その大前提を大きく崩す。
自由化の加速は、輸入農畜産物が一層国内市場に流れ込むのに加え、関税削減に伴い輸入差益を国内対策に回していた財源が細る「ダブルパンチ」となる。安倍晋三首相は国会答弁で「生産者の不安に向き合い、再生産へ十分な対策を講じる」と繰り返してきた。そうした首相答弁とは裏腹に、日本の財政は火の車で国の負担は早晩限界が来る。来年度の政府予算総額は初めて100兆円を超す。一方で債務負担は増え続ける社会保障費で歳入を大きく上回る。国民1人当たり借金は1000万円に上る。今秋の10パーセントへの消費税増税の中で、無駄な経費、補助削減の動きが一段と強まる。
既に稲作農家に最大で10アール当たり10万5000円助成する飼料用米の支援削減が声高に叫ばれ始めたのは、その証左だ。こうした中で、巨額の助成にもかかわらず規模拡大や生産性向上が進まない農業分野への批判が強まることを警戒する必要があるだろう。
米国抜きの11カ国によるTPP協定発効は、これまでの通商協議の地図を塗り替えかねない。前例のない農畜産物の自由化が進み、発効から約3カ月後の今年4月からは協定2年度目の一層の関税削減が迫られる。
最大で最も効果的な国内対策は、これ以上の自由化をしないことだ。TPP11発効は、その大前提を大きく崩す。
自由化の加速は、輸入農畜産物が一層国内市場に流れ込むのに加え、関税削減に伴い輸入差益を国内対策に回していた財源が細る「ダブルパンチ」となる。安倍晋三首相は国会答弁で「生産者の不安に向き合い、再生産へ十分な対策を講じる」と繰り返してきた。そうした首相答弁とは裏腹に、日本の財政は火の車で国の負担は早晩限界が来る。来年度の政府予算総額は初めて100兆円を超す。一方で債務負担は増え続ける社会保障費で歳入を大きく上回る。国民1人当たり借金は1000万円に上る。今秋の10パーセントへの消費税増税の中で、無駄な経費、補助削減の動きが一段と強まる。
既に稲作農家に最大で10アール当たり10万5000円助成する飼料用米の支援削減が声高に叫ばれ始めたのは、その証左だ。こうした中で、巨額の助成にもかかわらず規模拡大や生産性向上が進まない農業分野への批判が強まることを警戒する必要があるだろう。
安倍政権の「見切り発車」
まずは、幾多の課題を積み残したままの「見切り発車」の弊害だ。問題は多国間協議で国内産業、農業の打撃を最小限に抑える戦略が破たんしたにもかかわらず、推し進めたことだ。
TPPの本質は市場開放と地域の安全保障が密接に絡んだ「日米経済軍事同盟」だ。背景には膨張主義を強める中国への対抗がある。中国はTPPに備えるためインフラ投資と併せ「一帯一路」で活路を開こうとしている。こうした世界を二分する米中激突の中で、TPP論議は進んできた。だが結果的には米国抜きの11カ国が残り、次には今春の対米協議が控える結果となった。
国会審議も生煮えのままの「見切り発車」は、そもそも米国参加が前提で決めたいくつかの仕組みの整合性が問われる。TPP協定第6条の「見直し条項」は、米国の協定復帰の可能性がなくなった際の見直しを規定した。そして、実際にトランプ政権の復帰は全く見込めなくなった。明治大学の作山巧教授は日米2国間協議は実際には自由貿易協定(FTA)なのは明白と指摘。その上で、「日米FTA交渉開始が決定し、米国のTPP復帰の見込みがも込めなくなった今こそ、政府は協定見直しの約束を果たすべき」とする。当然であろう。
牛・豚のセーフガード発動基準やチーズの低関税枠から米国分を差し引かなければ、自由化の打撃は大きくなりかねない。このままでは、国産食肉価格を下支えするセーフガードは発動できず、戦略品目チーズの国産化にも逆風だ。前述したように、チーズ関税削減に伴い4年程度で制度は効かなくなる。
次に「代償」である。安倍首相はトランプ大統領の当選当初、「米国抜きでは意味がない。根本的な利益のバランスが崩れてしまう」と述べる一方で、「TPPは幅広い分野で21世紀型のルールを作るもの」とTPP推進に固執した。全ての通商交渉に関税大幅削減・撤廃を盛り込んだ「TPP基準」を採用すれば、国内農業への打撃は避けられない。既に米国の農業団体は「TPPを上回る譲歩」を迫る。強硬なTPP発効の「代償」そのものだ。
TPPの本質は市場開放と地域の安全保障が密接に絡んだ「日米経済軍事同盟」だ。背景には膨張主義を強める中国への対抗がある。中国はTPPに備えるためインフラ投資と併せ「一帯一路」で活路を開こうとしている。こうした世界を二分する米中激突の中で、TPP論議は進んできた。だが結果的には米国抜きの11カ国が残り、次には今春の対米協議が控える結果となった。
国会審議も生煮えのままの「見切り発車」は、そもそも米国参加が前提で決めたいくつかの仕組みの整合性が問われる。TPP協定第6条の「見直し条項」は、米国の協定復帰の可能性がなくなった際の見直しを規定した。そして、実際にトランプ政権の復帰は全く見込めなくなった。明治大学の作山巧教授は日米2国間協議は実際には自由貿易協定(FTA)なのは明白と指摘。その上で、「日米FTA交渉開始が決定し、米国のTPP復帰の見込みがも込めなくなった今こそ、政府は協定見直しの約束を果たすべき」とする。当然であろう。
牛・豚のセーフガード発動基準やチーズの低関税枠から米国分を差し引かなければ、自由化の打撃は大きくなりかねない。このままでは、国産食肉価格を下支えするセーフガードは発動できず、戦略品目チーズの国産化にも逆風だ。前述したように、チーズ関税削減に伴い4年程度で制度は効かなくなる。
次に「代償」である。安倍首相はトランプ大統領の当選当初、「米国抜きでは意味がない。根本的な利益のバランスが崩れてしまう」と述べる一方で、「TPPは幅広い分野で21世紀型のルールを作るもの」とTPP推進に固執した。全ての通商交渉に関税大幅削減・撤廃を盛り込んだ「TPP基準」を採用すれば、国内農業への打撃は避けられない。既に米国の農業団体は「TPPを上回る譲歩」を迫る。強硬なTPP発効の「代償」そのものだ。
農水省審議会の「形骸化」
重大な農政転換が続く中で、肝心の食料・農業・農村政策審議会が十分に機能しているのか。大きな疑問と疑念は、一昨年の加工原料乳補給金制度の抜本見直しの経過だ。こうした、畜酪制度の根幹にかかわる改定問題は当然、審議会畜産部会で議論を深めることが必須のはずだ。だが農水省は、現行指定生乳生産者団体制度の廃止など規制改革推進会議の提案を受け、与党との調整に大半の時間を費やした。2017年末の畜産部会の審議委員には結果報告しただけだ。これを審議会の「形骸化」と言わずに何と言うのか。
官邸農政による規制改革論議が先行し、審議会での専門家のやり取りが形骸化してはならない。こうした反省の上に立ち、2019年度畜産酪農政策価格論議を契機に再び活発な論議をすべきだ。
同審議会は、食料・農業・農村基本法第39条に基づき設置された農相の諮問機関だ。かつての農業基本法制下の農政審議会は、環境激変を踏まえたその後の日本の農政路線の在り方を議論し、指針を示してきた。だが、今の審議会は農水省の施策説明の場になっていないか。
一連の農政改革は、政府の規制改革推進会議が実態に基づかない急進的な見直しを提案。しかも、農政改革がいつの間にか農協改革、さらには全農改革にすり替わった。この高めのボールを受け、自民党が農業団体などとの調整を経て、収まりどころを探るケースが続いてきた。官邸農政を推進した前事務次官の奥原正明氏が、審議会よりも政府・与党調整を最重視た結果との見方が強い。2月からは次期基本計画の見直し論議も始まる。後任の末松広行事務次官となり、従来の審議会で談論風発に転換すべきだ。
官邸農政による規制改革論議が先行し、審議会での専門家のやり取りが形骸化してはならない。こうした反省の上に立ち、2019年度畜産酪農政策価格論議を契機に再び活発な論議をすべきだ。
同審議会は、食料・農業・農村基本法第39条に基づき設置された農相の諮問機関だ。かつての農業基本法制下の農政審議会は、環境激変を踏まえたその後の日本の農政路線の在り方を議論し、指針を示してきた。だが、今の審議会は農水省の施策説明の場になっていないか。
一連の農政改革は、政府の規制改革推進会議が実態に基づかない急進的な見直しを提案。しかも、農政改革がいつの間にか農協改革、さらには全農改革にすり替わった。この高めのボールを受け、自民党が農業団体などとの調整を経て、収まりどころを探るケースが続いてきた。官邸農政を推進した前事務次官の奥原正明氏が、審議会よりも政府・与党調整を最重視た結果との見方が強い。2月からは次期基本計画の見直し論議も始まる。後任の末松広行事務次官となり、従来の審議会で談論風発に転換すべきだ。
問題は規制改革の横やり
同審議会会長として2015年の食料・農業・農村基本計画策定にかかわった福島大学の生源寺真一教授は、「基本計画と無関係に政策が進むのはおかしい」と、規制改革論議の行方に懸念を表明している。まっとうな農政改革に向け、審議会の議論を通じ正常な軌道に乗せなければならない。
こうした事例は生乳制度改革にも踏襲された。規制会議は、独占的な生乳集荷で競争を阻害しているとして現行指定生乳生産者団体制度の廃止を求めた。こうした中で、同省は半世紀続いた酪農不足払い制度を廃止し、畜産経営安定法に組み込んだ。これまでの暫定法から恒久法に位置付けた点は良いが、制度の根幹だった指定団体の生乳一元集荷を廃止し生乳流通自由化へ移行した。改正畜安法下の生乳流通の変化は、新制度2年目となる2019年度の動きを注視する必要がある。
来年度畜酪政策の答申を巡り、畜産部会を開く。同部会では農相諮問事項の加工原料乳補給金単価、肉用子牛保証基準価格、関連政策などを議論するのは当然だ。だが、生産基盤の大きく揺らぎ、自由化の加速化が進む畜酪の危機的状況と将来展望も再度、意見を交わすべきではないか。指定団体への酪農家の結集力がどうなるのか。改正畜安法の検証と運用改善も欠かせない。
先の基本計画と連動し次期酪農・肉用牛近代化基本方針の論議も始まる。昨年末の第1回畜産部会は、委員17人のうち部会長をはじめ6人が欠席した。審議会の形骸化にもつながり看過できない事態だ。かつては、部会長が将来ビジョンを持ち論議を主導する時もあった。人選再考も含め審議会論議を充実する必要がある。
同日の日本乳業協会の宮原道夫会長(森永乳業社長)の指摘は重要だ。宮原氏は、一連の生乳制度改革に関し専門部会である畜産部会で議論しなかったことに疑問を呈し、酪肉近見直しでは「酪農・乳業実務関係者の意見をしっかり聞き反映すべき」と、審議会軽視にくぎを刺した。今回の畜酪論議を皮切りに、審議会重視を徹底すべきだ。
こうした事例は生乳制度改革にも踏襲された。規制会議は、独占的な生乳集荷で競争を阻害しているとして現行指定生乳生産者団体制度の廃止を求めた。こうした中で、同省は半世紀続いた酪農不足払い制度を廃止し、畜産経営安定法に組み込んだ。これまでの暫定法から恒久法に位置付けた点は良いが、制度の根幹だった指定団体の生乳一元集荷を廃止し生乳流通自由化へ移行した。改正畜安法下の生乳流通の変化は、新制度2年目となる2019年度の動きを注視する必要がある。
来年度畜酪政策の答申を巡り、畜産部会を開く。同部会では農相諮問事項の加工原料乳補給金単価、肉用子牛保証基準価格、関連政策などを議論するのは当然だ。だが、生産基盤の大きく揺らぎ、自由化の加速化が進む畜酪の危機的状況と将来展望も再度、意見を交わすべきではないか。指定団体への酪農家の結集力がどうなるのか。改正畜安法の検証と運用改善も欠かせない。
先の基本計画と連動し次期酪農・肉用牛近代化基本方針の論議も始まる。昨年末の第1回畜産部会は、委員17人のうち部会長をはじめ6人が欠席した。審議会の形骸化にもつながり看過できない事態だ。かつては、部会長が将来ビジョンを持ち論議を主導する時もあった。人選再考も含め審議会論議を充実する必要がある。
同日の日本乳業協会の宮原道夫会長(森永乳業社長)の指摘は重要だ。宮原氏は、一連の生乳制度改革に関し専門部会である畜産部会で議論しなかったことに疑問を呈し、酪肉近見直しでは「酪農・乳業実務関係者の意見をしっかり聞き反映すべき」と、審議会軽視にくぎを刺した。今回の畜酪論議を皮切りに、審議会重視を徹底すべきだ。
地域重視へ方向転換必要
安倍政権下で農業には「北風」ばかりだったが、ここに来て風向きが変わってきたことに注目したい。年明けの中央畜産会の新年会で、森山裕会長(元農相)は「規模拡大ばかりでなく、地域を支える家族農業も重視しなければならない」と公言した。年末の畜産部会の議論でも、肉用子牛補給金制度の見直し、新たな保証基準価格を決める際に「家族農業」の言葉が多く出た。
今年は国連の「家族農業の10年」がスタートする。安倍農政は強い農業、農業の成長産業化、輸出拡大の「3点セット」以外に柱がない。これでは大半の国内農家は持たない。農政転換すべきだ。
問題は、足元の生産基盤の瓦解、地域経済の弱体化にどう対応し、有効な政策を展開できるのか。最も大切なのは国内農業生産の拡大を通じた食料自給率向上と結びついた食料安全保障、食料主権を再び取り戻すことである。それには、広範に存在する家族酪農ネットワークを強めることが効果的だ。そのための役割こそ指定団体は担う必要がある。
(次回「透視眼」は4月号)
今年は国連の「家族農業の10年」がスタートする。安倍農政は強い農業、農業の成長産業化、輸出拡大の「3点セット」以外に柱がない。これでは大半の国内農家は持たない。農政転換すべきだ。
問題は、足元の生産基盤の瓦解、地域経済の弱体化にどう対応し、有効な政策を展開できるのか。最も大切なのは国内農業生産の拡大を通じた食料自給率向上と結びついた食料安全保障、食料主権を再び取り戻すことである。それには、広範に存在する家族酪農ネットワークを強めることが効果的だ。そのための役割こそ指定団体は担う必要がある。
(次回「透視眼」は4月号)
- 2025年 12月号
- 2025年 10月号
- 2025年 8月号
- 2025年 6月号
- 2025年 4月号
- 2025年 2月号
- 2025年 1月号
- 2024年 10月号
- 2024年 9月号
- 2024年 8月号
- 2024年 6月号
- 2024年 4月号
- 2024年 2月号
- 2024年 1月号
- 2023年 12月号
- 2023年 10月号
- 2023年 8月号
- 2023年 6月号
- 2023年 4月号
- 2023年 2月号
- 2023年 1月号
- 2022年 12月号
- 2022年 10月号
- 2022年 8月号
- 2022年 6月号
- 2022年 4月号
- 2022年 2月号
- 2022年 1月号
- 2021年 12月号
- 2021年 10月号
- 2021年 8月号
- 2021年 6月号
- 2021年 4月号
- 2021年 2月号
- 2021年 1月号
- 2020年 12月号
- 2020年 10月号
- 2020年 8月号
- 2020年 6月号
- 2020年 4月号
- 2020年 2月号
- 2020年 1月号
- 2019年 12月号
- 2019年 10月号
- 2019年 8月号
- 2019年 6月号
- 2019年 4月号
- 2019年 2月号
- 2019年 1月号
- 2018年 12月号
- 2018年 10月号
- 2018年 8月号
- 2018年 6月号
- 2018年 4月号
- 2018年 2月号
- 2018年 1月号
- 2017年 12月号
- 2017年 10月号
- 2017年 8月号
- 2017年 6月号
- 2017年 4月号
- 2017年 2月号
- 2017年 1月号
- 2016年 12月号
- 2016年 10月号
- 2016年 8月号
- 2016年 6月号
- 2016年 4月号
- 2016年 2月号
- 2016年 1月号


